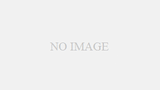〔アーカイブ・データ〕
・川本隆史「震災と倫理――絆・死別・物語りをめぐって」(所収:「第63回大会予稿集」)
・川本隆史「はしがき――「非常時」の出来事と倫理学」
(所収:『倫理学年報』第62集(2013年3月30日発行))
・高橋久一郎「総括質問の後で」(所収:『倫理学年報』第62集(2013年3月30日発行))
震災と倫理――絆・死別・物語りをめぐって
(所収:「第63回大会予稿集」)
川本隆史(共通課題実行委員・東京大学)
□課題設定の経緯およびねらい
自由課題とは別立ての共通課題を設け、発表および討議の記録を残すようになったのは、第十六回大会の「実存と倫理」(金沢大学、一九六五年十月)を嚆矢とする。その後、第四十四回大会(広島大学、一九九三年十月)の会員総会において「共通課題設定の新方式」(課題設定時期を早め、一連の業務を設定委員会と実行委員会とで分担する)が提案・承認され、第四十六回大会(岩手大学、一九九五年十月)の共通課題「性」より新方式が実施の運びとなった。さらに第五十九回大会(筑波大学、二〇〇八年十月)以降、複数の「主題別討議」を大会二日目に設けることによって、共通課題のスリム化(時間および提題者数)が図られ、現在にいたっている。
本課題はこうした改革路線に沿うものであると同時に、二〇一一年度の第六十二回大会(富山大学)初日の「特別企画」を受けるかたちで設定された。まずは共通課題設定委員会による課題設定の趣旨(原案)の冒頭を引用する。
未曾有とも、千年に一度とも言われた東日本大震災を被災して半年経て、東北各地の震災・津波からの復興・復旧も、福島第一原子力発電所の事故収束もはかばかしく進んでいない。日本倫理学会としては、今年度大会において緊急「特別企画」として「倫理学(の研究者)は震災・原発事故にどう向き合えるのか、何ができ/できないのか」を問うた。次年度六十三回大会共通課題は、こうした問いの先で、あらためて問いうるものを間い直し、問い重ねることとしたい。
従来であれば、設定委員会から付託された共通課題を複数の問題群へと分節化し、それぞれにふさわしい報告者を絞り込むという過程を踏むべきところだが、今回はあえて逆向きに進めた。それは当該問題領域の専門家があらかじめ育成されていたわけではない、本テーマが要請するところでもあっただろう。すなわち、複数の重要事項(Sache)から登場人物(Person)へとトップダウン式に策定(「人材発掘」!)するのではなく、まず適材と思われるPersonに白羽の矢を立て、その人物がボトムアップで積み上げたSacheを全面展開してもらうという方針を採らざるを得なかったゆえんである。
□キーワードによる主題の分節化
第三十一期第五回評議員会(二〇一一年十二月十七日)において承認された報告者三名(福嶋揚、宮野真生子、鷲田清一〔アイウエオ順〕)との意見交換を経て、三者それぞれに「キーワード」を割り当て、それを共通課題の副題に併記することとした。三つの単語をもって、語り手および聴き手の関心の緩やかな結集軸とすることにより、論議がいたずらに拡散するのを防げるのではないかと期待している。
(1)三・一一を「原発震災」と受けとめ、「キリスト教研究の視点」から「黄金律」の読み直しを試みようとする福嶋報告は、「絆」をキーワードとする。震災・原発事故後に高まった「絆」の大合唱を批判的に聴き取り、「絆」という語句の有する切実さと危うさを倫理学の観点からきちんと読み分けながら、「黄金律」の検討へと踏み込んでいく。
(2)最晩年の田辺元がたどり着いた「死における実存共同」の可能性を探ろうとする宮野報告には、「死別」というキーワードをあてがっている。「生き残ってしまった」疾しさ、もしくは「死別」という傷みを手がかりに、近代日本哲学史の遺産を点検する。
(3)震災直後より精力的な社会発信を続けている鷲田会員には、近作『語りきれないこと――危機と傷みの哲学』(角川学芸出版二〇一二)を踏まえつつ、「物語り」を軸に持論を展開するよう要請した。「東北の震災と「倫理学」」という報告タイトルが予告されている。
なお当日は三人の報告に対する総括コメンテータを配し、大会二日目の「主題別討議=原発事故について倫理学は何が言えるか」との連携を図ろうと考えている。また初日のワークショップにおいても、関連するテーマが論じられると聞き及ぶ。三日間の大会の掉尾を飾るべく、会員の叡智を突き合わせ、異見は異見として尊重する「熟議」(deliberation)の場を実現したい。
はしがき――「非常時」の出来事と倫理学
(所収:『倫理学年報』第62集(2013年3月30日発行))
共通課題実行委員(金井淑子、川本隆史、神崎繁、高橋久一郎)
一 課題設定の背景および経緯
自由課題とは別立ての共通課題を設け、発表および討議の記録を残すようになったのは、第16回大会の「実存と倫理」(金沢大学、一九六五年一〇月)を嚆矢とする。その後、第44回大会(広島大学、一九九三年一〇月)の会員総会において「共通課題設定の新方式」(課題設定時期を早め、一連の業務を設定委員会と実行委員会とで分担する)が提案・承認され、第46回大会(岩手大学、一九九五年一〇月)の共通課題「性」より新方式が実施の運びとなった。さらに第59回大会(筑波大学、二〇〇八年一〇月)以降、複数の「主題別討議」を大会二日目に設けることによって、共通課題のスリム化(時間配分および提題者数)が図られ、現在にいたっている。
本課題はこうした改革路線に沿うものであると同時に、二〇一一年度の第62回大会(富山大学)初日の「特別企画」を引き継ぐかたちで設定された。まずは共通課題設定委員会が起草した課題設定の趣旨(原案)の冒頭を引用する。
未曾有とも、千年に一度とも言われた東日本大震災を被災して半年経て、東北各地の震災・津波からの復興・復旧も、福島第一原子力発電所の事故収束もはかばかしく進んでいない。日本倫理学会としては、今年度大会において緊急「特別企画」として「倫理学(の研究者)は震災・原発事故にどう向き合えるのか、何ができ/できないのか」を問うた。次年度63回大会共通課題は、こうした問いの先で、あらためて問いうるものを問い直し、問い重ねることとしたい。
従来であれば、設定委員会から付託された共通課題を複数の問題群へと区分けし、それぞれにふさわしい報告者を絞り込むという過程を踏むのが常道だが、今回はむしろ逆向きに進めた。それは当該問題領域の専門家が前もって育成されていたわけではない、本テーマが要請するところでもあっただろう。すなわち、既定の重要事項(Sache)から登場人物(Person)へとトップダウン式に策定(「人材発掘」!)するのではなく、適材と思われるPersonに自羽の矢を立て、その人物がボトムアップで積み上げたSacheを全面展開してもらうという方針を採らざるを得なかった所以に他ならない。
二 三つの単語による主題の分節化
第31期第5回評議員会(二〇一一年一二月一七日)において承認された報告者三名(福嶋揚、宮野真生子、鷲田清一)との意見交換を経て、三者それぞれに「キーワード」を割り振り、それらを共通課題の副題に併記することとした。三つの単語をもって、語り手および聴き手の関心の緩やかな参照枠とすることによって、論議がいたずらに拡散するのを防げるのではないかとの目論見に基づいている。
(1)三・一一を「原発震災」と受けとり、「キリスト教研究の視点」から「黄金律」の再解釈を試みようとする福嶋報告は、「絆」をキーワードとする。震災・原発事故後に高まった「絆」の大合唱を批判的に聴き取り、「絆」という語句の有する切実さと危うさを倫理学の観点から精確に読み分けながら、「黄金律」の検討へと踏み込んでいくことを期待した。
(2)最晩年の田辺元がたどり着いた「死における実存協同」の可能性を探ろうとする宮野報告には、「死別」というキーワードに照準する立論をお願いした。「生き残ってしまった」疾しさ、もしくは「死別」という傷みを手がかりにしながら、近代日本哲学史の遺産が「震災と倫理」という土俵のどこで、どのように生かせるのかを精査する。
(3)阪神淡路大震災の体験をひとつの契機として「臨床哲学」を提唱するようになり、東日本大震災の直後から精力的な社会発信を続けてきた鷲田会員には、近作『語りきれないこと――危機と傷みの哲学』(角川oneテーマ21、角川学芸出版、二〇一二年)の延長線上において、「物語り」を軸に持説を開陳するよう促した。
なお当日は、三人の報告に対する二名の総括コメンテータ(高橋久一郎、田島正樹)と司会者二名(金井淑子、川本隆史)を配し、初日のワークショップ、大会二日目の「主題別討議=原発事故について倫理学は何が言えるか」との連携を企てた。三日間の大会の掉尾を飾るべく、会員の叡智を突き合わせ、異見は異見として尊重しあう「熟議」(deliberation)の場を実現しようと努めたのだが、その成否のほどは会場参加者および本年報の読者の判断に委ねざるを得ない。
三 キーワードをめぐる争点の深化・拡大
この「はしがき」に続いて、大会での質疑・討議を踏まえた報告者および総括質問者の論考四本が並んでいる。以下では、あらずもがなの総花的イントロダクションに代えて、〈絆〉、〈死別〉、〈物語り〉に集約される三つの争点がどこまで深まり拡がったかを概観しておくとしよう。各論文を読みつなぐ際の一助となるならば、これで実行委員の任務もどうにか完了である。
(1)〈絆〉ということ。
「三・一一以後」の現在を「震災直前」もしくは「原発震災の渦中」と捉える福嶋論文は、「震災後に国策や巨大資本によって喧伝されてきた「絆」」への対抗構想として、「共に生き延びるための、人と人の互恵的な関係の、自発的で多元的な、創造と活性化」を対置する。「他者の人格と尊厳と独立を脅かし、病や死の危険を強制する「絆」とは、生命に敵対する死の「絆」、すなわち関係創造を装った関係喪失でしかない」との断が下されている。
宮野論文は「絆」を直接のターゲットとするものではないけれども、「震災の直後から、この災害を「日本」というキーワードで語ろうとする言説」に対する「違和感」を端的に表明している。この感覚を発条として、「絆」ならぬ「実存協同」に向かおうとする田辺元の晩年の思索が丹念にたどられた。
鷲田論文もまた、「個人から個人への支援の言葉一つとっても、「がんばれ」という激励の言葉が人を傷つける言葉へと反転することをわたしたちは思い知ったし、「絆」という、わたしたちがなによりも共有すべき理念が傍観するだけの人のアリバイを表明する言葉に変容してしまっているという苦い認識も得た」との反省を怠っていない。
そうした一連の「絆」言説の「位置価」を批判的に解明するとともに、福嶋論文が(直江清隆会員の指摘を受けて)注記している、被災当事者が自主的に用いた「絆」ということばの痛切な響きにも耳を傾けねばならないだろう。
(2)〈死別〉ということ。
福嶋論文と鷲田論文は、「死」や「死別」に関して間接的な言及に抑えている。前者は「〔イエスの〕死が単なる死去を超える一種の贈与の出来事として再発見され解釈されるようになっていったこと」への注目を、後者は震災がもたらした「破砕と喪失」からの「語りなおし」を物静かに勧めているのである。
「今日のいわゆる原子力時代」を「死の時代」であると観じた田辺元が、「死復活の転換の瞬間から、持続する生の未来へと踏み出すための、喜びのありかを求める必要を訴えた」。そのポイントを宮野論文は、次のように敷衍している「あのひとはもういない。しかし、その喪失を通じて、残された者は自らの生を感受する。その生は死によって届けられるものであり、そのとき、残された者は、いなくなってしまった者を、存在とは別の形で感じている。目の前に存在はしていないにもかかわらず、たしかに私の傍らにあって、私の生を照らし出すもの、それが死者であり、その死者に面して、残された者は自らを生者として自覚する」。
宮野報告については、総括質問者の田島正樹氏(千葉大学文学部/非会員)が「死を自己の死としてではなく、他者の死、死者との関わりの問題として捉えようとする点に関しては、おおむね賛成できる」としながらも、田辺元の論が「死者との関わりというには、余りに抽象的・理論的にすぎるという印象はぬぐえない」とのコメントを綴っている(同氏のブログ「ララビアータ」田島正樹の哲学的断想」http://blog.livedoor.jp/easter1916/の2012年10月16日「倫理学会参観記」の項)。一方で死者との「実存協同」という普遍的原理を探究しながら、他方で「人は死において、ひとりひとりその名を呼ばれなければならないものなのだ」とする詩人の直観(石原吉郎『望郷と海』みすず書房、二〇一二年、二頁)を手放さないこと、こうした双対的なアプローチを鍛え上げる地道な努力が私たちに求められているのではなかろうか。
ちなみに同じ総括質問者の高橋久一郎会員は、「三つの死」という分類枠をあえて打ち出そうとした。すなわち「〔1〕今回の地震と津波で直接的に亡くなった人、〔2〕それの伴う移住や、原発事故がなかったならば亡くなることはなかったであろう人、〔3〕そして、生物としての「死」というのではなくとも、さまざまに「生のあり方」を奪われた、あるいは、奪われつつある人」の謂いである。「三つ目の死」に向き合い、「このまま推移すれば、寄り添うことも忖度することもなくなる、つまり、「なかったことにする」になるのではないかとの思い」に発する高橋会員の〈死別〉論を、「震災死者」をひと括りにしようとする力学への抵抗の試みとして受けとめたい。
(3)〈物語り〉ということ。
福嶋論文を「山上の垂訓」(マタィ福音書の五~七章)という〈物語り〉の編み直しと読むこともできようし、「「日本」あるいは「無常」という語り」を警戒する宮野論文も、田辺元がマラルメの象徴詩『双賽一擲』を「運命を生かして協同の自由を実現する路」を示す〈物語り〉として読み込んだ点を評価しようとしている。
〈物語り〉を基軸にしてほしい旨を準備段階で伝えた鷲田報告だったが、本番ではそのリクエストを巧みにかわし、震災被災地の方々に対して「倫理学に何ができるか?」という問いそのものを吟味するところから説き起こした。その鷲田会員の〈物語り〉論の片鱗は(本人も引用している)以下の文章から窺い知ることができよう。
「震災で、津波で、原発事故で、家族を、職場を、そして故郷を奪われた人たちは、これまでおのが人生をそのまわりにとりまとめてきた軸とでも言うべきものを失い、自己の生存について一から語りなおすことを迫られています。語りなおしとは、じぶんのこれまでの経験をこれまでとは違う糸で縫いなおすということです。縫いなおせば柄も変わります。感情を縫いなおすのですから、針のその一刺し一刺しが、ちりちりと、ずきずきと痛むにちがいありません。 被災地外の場所で、個々のわたしたちがしなければならないことは、まずはそういう語りなおしの過程に思いをはせつづけること、出来事の「記念」ではなく、きつい痛みをともなう癒えのプロセスを、そのプロセスとおなじく区切りなく「祈念」しつづけることだろうと思います。」(前掲『語りきれないこと』四~五頁)
「哲学/倫理学は歴史的な日付をもった出来事にいかにかかわるのか?」(普遍的な理論・理念と個別具体的な出来事・状況との関係如何)という問題を提起した鷲田報告に対しては、「物語とは、出来事から意味を抽出する記述ないしは意味が生成する過程の記述と言えるだろう」と解する田島正樹氏が少々手厳しい論評を加えている。「鷲田氏は、ヘーゲルのように、出来事を理念の展開に解消するのでも、逆に理念を社会的事象に解消するのでもなく、それらを媒介する倫理学の社会性のようなものに言及されたようである。このような媒介がどのように可能なのかは不明であるが、おそらく氏は、倫理学者がさまざまの現場に赴いて、言論の取りまとめや話し合いの交通整理をする役割を、念頭に置かれているのだろう。しかしいずれにせよ、ここでも欠けているのは、それが共通基盤や共通了解に依存しない政治闘争の現場だという認識である」と(前掲ブログ)。
鷲田論文には、田島氏に対する明示的なリプライは書き込まれていない。けれども「「倫理学研究者」であるということをいつでも棚上げにして「市民」として活動できることと、この時代の、この国の社会のありようから一定の距離をとることが委託されていることという、「倫理学研究者」が市民かつ職業人として内蔵しているこの二重性から、目を離してはならないとおもう」と語る鷲田会員の弁が、「闘争と裁きの中でうまれつつある」「物語としての正義観念」への「公共的注視」を力説する田島氏への「応答」(「答えられなくても応えること」という意味での!)ともなっているのではないか。この推定が、共通課題実行委員という「割り当てられた職務」に拘泥する「理性の私的使用」が下した憶断に過ぎないのか、はたまた「ある集団や組織のなかでおのれに配置された地位や業務から離れて」発揮される「理性の公共的使用」の帰結なのかについては、広く会員・読者の判定を仰ぐことにしたい。
いずれにせよ〈物語り〉や「言説のポジショナリティ」をめぐっては、おそらく本年の第64回大会の共通課題「倫理学は生き方の指針を与えることができるのか」において、論者とテーマを変えての熱い議論の応酬が続くに相違なかろう。実行委員の一名が次期の共通課題の設定に関与したという恵まれた事情もある。本共通課題(「震災と倫理」)の継承と発展が松山の地でどのように繰り広げられるかを、刮目して見守ろうと思う。
【付記】共通課題の全体討議については、実行委員がとりまとめた記録や論点整理を『倫理学年報』に掲載するのを常としてきた。しかしながら今回に関しては、全体討議から受けた示唆や教訓を四名の寄稿文に適宜盛り込むよう依頼したにとどめている。このたびの震災が“「非常時」の出来事”(鷲田論文)であった以上、これを扱うのに通常のやり方ではなく、一種の〈応急措置〉をやむなく採用したことを了とされたい。もちろん当日の録音データは事務局が保管しており、別のかたちで開示する用意はある。
なお高橋論文の末尾に「今回の原発事故との関わりで〔……〕、「生命の倫理」の可能性と重要性について考えるワークショップを継続的に開催する」という提案が明記されている。関係者の合議・合意を積み重ねながら、この「忘れてはならないこと」を語りあう企画を持続する方向を探るつもりである。
(文責=川本隆史)
総括質問の後で
(所収:『倫理学年報』第62集(2013年3月30日発行))
高橋久一郎
今大会の共通課題「震災と倫理」に関して、(震災以後、積極的な発言および活動をしていることから、非会員であるが総括質問者をお願いした)田島正樹さんと私は、連携して開催されたワークショップ「科学技術文明史と倫理」(今村純子、黒住真、最首悟、丹波博紀)と、主題別討議「原発事故について倫理学は何が言えるか」(寺本剛、福永真弓、本田康二郎)に出席した上でコメントと質問を行った。
田島さんは、すでにそのホームページ『ララビアータ』において「参観記」を公表されており、それで十分であるとのことなので、ここでは私の視点から、今回の課題について、二つの項目、つまり、多くの提題に見られた「生命の倫理とリスクの論理」、語り・聴くこととの関わりで私の気がかりとなった「三つの死」という項目で纏め、最後に「一つの提案」をしておきたい。
その前に、今回の震災、「原発事故」との絡みでの私自身の反応について記しておく。実は私自身は震災の時には日本にはおらず、4月も半ばになってから帰国した。そんな状態、つまり、いわば「安全な状態」で最初の一月ほどの推移を見ていたわけだが、それでも、いや「それだけに」だろうか、日本の「哲学界」は何か「音無し」のように思われ、もどかしく感じられた。とはいえ、鬼頭さんたちの集会や、家人が試みていた(夏休みだけでも子供を「戸外で遊べる場所に」という)活動にちょっとだけ関わり、デモにも何度か参加した程度で、それ以上に積極的には動こうとはしなかった。
昨年度の倫理学会が「特別」ワークショップを行うということになり、提題者の一人として、「原発事故ついて、「やられっちゃった」という感覚もあり、困惑している」という趣旨の発言をした。事故について、その倫理を考える「学徒」というより先に、「被害者」という意識が先ず生じたことに困惑したからである(私は福島県の郡山出身であり、母は微妙な地域に(自分で作った作物も食べながら)住んでいる)。地震のために流れた「応用哲学会」を改めて今年4月千葉大で開催するにあたっても、技術的な問題に絡んで原発に関する企画を設けて頂き、特定質問者として発言の機会をえたが、私は困惑したままであった。今も、どこか困惑したままでいる。
書いている時期が分かってしまうが、今回の総選挙の結果、国民は、それとして意識しているかどうかはともかく、「原発」という国策を維持することを改めて選んだように思う。その上で、では倫理学は何を語るのか?
「生命の倫理とリスクの論理」
リスクの論理は、ある意味で分かりやすい。意識してはいないとしても、われわれはいたるところでリスク判断を日々行っているから、説明されれば、テクニカルな部分でフォローできないところはあったとしても、その論理は一応分かるからである。だからこそ、有効な分析の方法として盛んに研究されてきたし、実際、うまく使えば優れた分析の方法であるのだ。その上でなされるある種の「提案」に説得されないとすれば、多くの場合、リスクの「見積もり」の不一致であって、必ずしも枠組みそのものへの疑問であるわけではない。
原発については、実質上「リスク・ゼロ」だと説明され、多くの人は、半信半疑のところがあっても納得してきた、というのが実情だと思う。もちろん、何についてであれ「リスク・ゼロ」というのはありえないことである、だから、そこには、何らかのそうであって欲しいという願望があったことも事実である。しかし、何らかの決定を行うとすれば、どこかで割り切らなければならない。「割り切り」は、利益と不利益が交差する点より下ではありえない。それを満たしてくれていると思ったのだ。
反対していた人たちもリスクを明確に語ることはできなかった。あれこれの事故がおこる確率のことだけではない。その確率を最終的にどのように評価するかについては考えが別れることになったとしても、個々の要因の見積もりそのものについては、二桁ぐらいは異なっていたように思うが、それだけ見れば、事の性格上、さほど大きな対立ではない。さまざまな要因が重なっても「これほどの事故がおこる」とは反対派の人も予測していなかったのではないかと思う。だから、何らかの事故がおこってしまったときの、その事故がもたらす不利益の大きさについての分析と評価、そして対応の仕方については、いずれにせよ軽視されたところがある。この評価は、そうした事故をどのように考えるかに跳ね返ってくる。しかし、この評価も、ベースとしては二桁ぐらいの差異である。だが、ある事故が起こる確率の二桁は、素人目には、あえて言えば「大差ない」のに対して、その事故のもたらす不利益の二桁の違いは、素人にはそれとは比較にならないほど大きい。ここで浮かび上がってきた「不利益」は「人の命」である。
子供を連れて逃げた母親がいる。留まった母親もいる。どちらにも賞賛と非難がなされた。どうしてだろうか?交通事故で子供が死ぬ可能性があるからといって、自動車のない場所に逃げようとはしない。事故の可能性があるからといって、直ちに「反対」ということにはならない。リスクよりも利益が大きいと考えている。しかし、今回、原発については、リスクが分かっていないということが分かってしまった。母親たちだけでなく、再稼働しないように求める人々に、そして今回の提題の幾つかにも見られた「生命の倫理」は、こうした事例においては「リスクの論理」が機能しないのではないか、あるいは、機能するまで(つまりリスクが分かるまで繰り返して)使ってはならないのではないか、という問いかけであった。
私は、この問いかけがなされたことを、そのような問いかけがなされねばならなかったことは残念なことであるが、倫理学的にはかなり大きな意味があると考えたい。ある種の不適切さを承知の上で言えば、母親たちの行動に典型的に示された生命の倫理は、統治のためのリスクの論理を優先する男性の論理に対する「補完」ではない「倫理」でありうることを示したと思うからである。
「三つの死」
今回の地震と津波で直接的に亡くなった人、それの伴う移住や、原発事故がなかったならば亡くなることはなかったであろう人、そして、生物としての「死」というのではなくとも、さまざまに「生のあり方」を奪われた、あるいは、奪われつつある人がいる。
生じてしまったことについては元に戻すことができないから、何らか「補償」を考えることになる。「補償する」ことは、どのような補償が「ふさわしい」補償であるかという本質的な問題には立ち入らないとしても、いわゆる金銭的なことだけで「チャラにする」ことのできることではない。田島さんのいうような意味での「裁き」が不可欠であるかどうかはともかく、少なくとも(何を甘っちょろいと言われようが)「同じようなことを繰り返さない」術を探ることとセットになっているように思う。しかし、今回の事故で明らかになったのは、リスクの論理がまさに「補償でチャラにできる」と考えていること、「繰り返さない」とは考えていないことであった。戯画化して言えば、「起こらないはずのことが起こったのであり、したがって、しばらくは起こらない」と考えているようである。何も変わっていないし、変えようとしない。変えないことが、その論理の背景にある合理性に反する(とまでは断言できないとしても、今の状況から計算するならば(長期的にはもとより短期的にも)反する疑いが極めて大きい)にもかかわらずである。
どうしてなのか?三つ目の死との関わりで、席上「ある種の退廃」といった言い方をしたことに関して、終了後「被災者が堕落しているというのか」との質問を受けた。言葉を言い換えながら慎重に言ったつもりだったが、やはり、あのコンテクストでは不適切であり、当然の反応であった。しかし、「生き甲斐を失っている」とか「PTSD 現象がある」といった、「不幸」を語る語り方だけではすまない、何か未だうまく表現できないが、「(精神の)死」とでも言うべきものを感じている。阪神大震災の時と比べると、かなりの数の人が生活を回復できない懼れはかなり大きいように思われる。そのことに伴う感覚が「退廃」ということだった。そしてそれは、いわゆる「被災者」だけのことではない。自分の言動を振り返って「懺悔しよう」ということではない。「やられちゃった」という感覚は、確かに居直りぎみではあるが、現状ではそれなりに真っ当な感覚であると思っている。つまり、何人かの倫理学者が示したような過去のあり方への「反省」は、「推進者」たちが反省していない状況では、必要ないし、すべきでもないと思っている。
やや大げさな言い方をすれば、一般的には、「死者」とは、文字通りには対話することのできないある意味では絶対的な「他者」である。こうした他者に対しては、寄り添い、懐かしみ、そして、その思いを「忖度する」しかない。第三の「死者」という言い方をしたのは、このまま推移すれば、寄り添うことも忖度することもなくなる、つまり、「なかったことにする」ことになるのではないかとの思いがあったからである。「なかったことにする」のは何か?
現状について田島さんは、共通の理念や了解がないところでなされる「政治闘争」という問題場面を強調している。それはほぼ正しいと考えるが、倫理学が論ずる場面は、「常識」や「伝統」とされるなかなか「変わらない」共通理解の吟味にあるという言い方をしたいと思う。そして、そうした共通理解の一つは、政治的な課題に引き寄せられた言い方になるが、「日本は「強盛大国」でなければならない」という理解である。
「一つの提案」
ある種の「罪」に関しては「時効」という考え方には反対もあろうが、長い目で見れば「忘れる」ことは大事なことであると思う。しかし、「しばらく」は忘れてはならないことがある。私の提案は、今回の原発事故との関わりで、というのは論点が拡散してしまわないためであるが、「生命の倫理」の可能性と重要性について考えるワークショップを継続的に開催することである。もちろん、誰かがワークショップとして申し出れば行うことはできるわけだが、「誰かの申し出た企画」というだけでなく、日本倫理学会の継続企画として行うということである。今回の共通課題の委員である、金井淑子、川本隆史、神崎繁、そして私が一回ずつ「後始末」ということで担当すれば、四回はできる。あるいは、さらに、提題者である福嶋揚、宮野真生子、鷲田清一の各氏にもお願いすれば、七回できる。
最後に、震災以前の俳句と、以後の短歌・俳句を二つずつ、
どの子にも涼しく風の吹く日かな 飯田龍太
日向ぼこ地球が回つてゐたるとは 猪口節子
爆風のやうに桜花は白く咲き三度目の原爆かくもしづけき 川野里子
産むからだ産みたいからだ産むかもしれないからだ 怖れるからだ夏を白くす 米川千嘉子
双子なら同じ死顔桃の花 照井翠
鬼哭とは人が泣くこと夜の梅 高野ムツオ
(たかはし きゅういちろう・千葉大学)