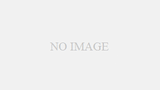〔アーカイブ・データ〕
・「第64回大会報告集」
※『倫理学年報』第63集の会務報告には詳しい報告が掲載されていないので、本アーカイブに掲載しない。
・(関連論文)米田祐介「〈核災〉と〈いのち〉の選別」、金井淑子・竹内聖一編『ケアの始まる場所――哲学・倫理学・社会学・教育学からの11章』ナカニシヤ出版(2015年2月27日発行)
・(関連論文)米田祐介「フクシマとサガミハラが投げかけるもの―「生産性」の2010年代、事件後に人間の尊厳について語るということ―」『立正大学哲学会紀要』第15号(2020年3月発行)
・(当日資料)米田祐介「〈核災〉と〈いのち〉の選別――「選ばないことを選ぶこと」の危機――」
第64回大会報告集
東日本大震災から学ぶ(1) 「女・こどもの倫理」
実施責任者 高橋 久一郎(千葉大学)
東日本大震災からのテーマという、何回か継続的に行いたいと考えているワークショップの全体としての狙いは、(私の「もくろみ」としては)『年報』に載せた昨年度の統一テーマの総括で述べたように、「生命」という価値を基軸に、これから先の倫理を考える上で、この大震災から見えてきた幾つかの核となる概念、例えば、リベラルといった理念やリスク分析といった手法の意義(と限界)を検討し、必要ならば大きな枠組みの中でのそれらの位置づけを考え直す可能性についての議論を試みることにある。
「余りに大きすぎる風呂敷」を拡げていると思われようが、ワークショップだからこそ拡げられる風呂敷だと考えている。その上で、今回のワークショップで狙いは、基本的にリベラルな枠組みのもとにある現代の倫理「学」において、「女・こどもの倫理」は無視されてはならないマイノリティの「要求」であるというだけではなく、むしろ「女・こどもの倫理」こそが、普遍的な倫理の枠組みである可能性を考えることにある。
これまた「大風呂敷」と思われるだろうが、敢えて挑発的な言い方をすれば、女は人類の半分であり、それに子供を加えれば、それだけで「女・こども」はすでに(さらに老人を加えるならば圧倒的に)マジョリティである。「女・こども」はマイノリティではないのだ。そして、この確認の上に、さらに挑発的な言い方をすれば、マジョリティは、その主張する倫理が普遍的であることを、リベラルがそうしてきたように、さまざまな批判に耐えつつ、主張し正当化しなければならない。しかもその正当化は、共に生きるマイノリティを自らの枠組みの中に相応しく包摂しつつなされなければならない。しかし、ここに問題が生ずる。普遍的な枠組みであろうとするマジョリティの倫理であるリベラルはこれまで、マイノリティに対しては何らかパターナリスティックな対応をしてきたし、せざるをえなかった。「女・こどもの倫理」は、この問題を回避できるか? あるいは、マイノリテイを気遣う普遍的な倫理においてパターナリズムは、「回避すべきことではなく、雄々しく(と敢えて記すが)引き受けるべきことであるのではないか」ということを考えるステップになれればよいと思っている。
今回の提題は、しかし、具体的な問題についての紹介と検討から始まる。具体的な場面・現実から語ることは、こうした「超越的な論理」を考えることと矛盾したり、対立したりすることにはならない。いやむしろ、今回の震災は、比喩的な言い方でしかないが、「女・こどもの倫理を中心にして倫理のあり方の全体を裏返してみる」ことを促しているように思っている。そしてそれは、具体的な事例をどのように理解するかに掛かっている。
お二人に提題をお願いした。米田さんは、「〈いのち〉の選別」という問題から、福永さんは、「ケア」ということの意義から、流通するマジョリテイの論理の、余り好きな言い方ではないが、「脱中心化」を試み、様々にありうる議論の取りあえずの出発点を示して頂くことになる。
原発災害と〈いのち〉の選別(仮題)
米田 祐介(立正大学)
「第一原発事故発生の前に生まれた子どものケアはできる。でも内部被曝している私には、胎児のケアはできないから……もう妊娠はあきらめた」。福島に住む30代の女性は語る。またある20代の女性は吐き捨てる。「なんかさ、私たち、モルモットみたいだよね。……バカにするなって言いたい。私は子どもを産んでやる。放射能汚染でエイリアンみたいになった子どもを産んでやる」。原発事故により飛散した放射能は、否応なく「無実の場」めがけて襲いかかる。生の側にとどまった福島の女性たちは、いま、産むか否かという苦悩のなかで不安を生きている。周囲の視線にさらされ恐怖を生きている。そして、わずかとはいえ、人知れず中絶を選んだ女性たちがいる。
他方で、放射能を浴びても妊産褥婦および胎児・乳児の健康に影響を及ぼす可能性はなく、したがって、安心して生活できることを伝える言説がある(総線量100ミリシーベルト以下、日本産婦人科医会研修ニュース「放射能汚染に関する基礎知識と現実的対応」)。ここで問題にしたいのは、実際に健康に影響があるかないかではなく「安心して生活できる」ことの内実である。本多(2012)がいみじくも指摘しているように、すなわちこうした言説は、被曝によって障害児や先天異常(奇形)児が生まれる可能性はないから安心してよい、ということを含意してはいないか。言い換えるならば、障害児や先天異常(奇形)児が生まれることは不幸なことであり、生まれないほうがよい、という価値規範を下敷きにしているのである。福島の女性たちは、中絶や妊娠自己規制に不安を抱え、あるいは追い詰つめられ、こうしたマジョリテイの合理的価値規範にさらされている。
もっといえば、このような県単位、いや、それを超えた範囲での不安の広がりは、「不当」な原発事故による「正当な不安」とは裏腹に、いわば「課題ある不安」すなわち優生思想の隆起にさえつながるものがあるのではないか。だとしたら、こうした状況下における中絶は、女性の自己決定に基づくものといえるのか。かりに出生前診断後に、中絶しているわけではなくとも、出生前診断と同じ論理・価値規範に基づいて行われるということはないだろうか。倫理的許容範囲はどこまでか。いまや、福島の女性たちは一身に負荷を背負い込むことになった。
本発表では、このような問題意識から、〈産むこと〉をめぐって福島の女性たちが置かれている状況を検討することを通じて〈いのち〉の選別を再考する。それはとりもなおさず、正常/異常という分割線をひくことにおいて駆動する近代的権力への対抗倫理を模索する試みでもあり、その場合、障害者運動と女性運動という二つの歴史的コンテクストからの福島の女/母たちへの言及可能性を視野にいれてみたい。
【参考文献】
・大橋由香子 2012 「しがらみ、なりゆき、あきらめの中での、一人ひとりの選択を大切にしたい」近藤和子/大橋由香子編『福島原発事故と女たち――出会いをつなぐ』梨の本舎
・小宮純一 2012 「東日本大震災下の子どもと女性(3) 「あの日」から1年 苦悩を抱え、生き抜く」『Sexuality』56 エイデル研究所・本多創史 2012 「再帰する優生思想」赤坂憲雄/小熊英二編『「辺境」からはじまる――東京/東北論』明石書店
福島原発事故、女、コミュニティ:ケアのもつ文脈と構造化された選択肢
福永 真弓(大阪府立大学)
東日本大震災の後、コミュニテイの再生が様々な難題を解決する妙薬のように語られる様を、社会学者の吉原直樹は、「コミュニティインフレーション」と呼んだ(伊豫谷、斎藤、吉原 2013)。長くコミュニティを研究の対象としてきた吉原は、「なかったけど、あった」コミュニティの構築、その規範化、強調が、どのような影響を実際に地域社会と人々にもたらしているのか、もたらそうとしているのかを注視する必要を指摘している。
「人の命のほうが大事ですよね。村残すより、人助けてやんなくてどうすんだっていう」(長谷川義宗さんの言葉、土井敏邦監督、2012『飯館村 故郷を追われる村人たち』より)。
人なのか、村(町、市)なのか。二項対立で語られるコミュニティの再生をめぐる言説は、人びとが抱える複雑な思いやニーズの多様さ、それぞれが求める福利の描き方の多様さ、そのための選択肢を選ぶという自由があること、必要であることを隠してしまう。
また、コミュニティの指す範囲が、暮らしている実感のある場所から想像的な共同体としての大きなコミュニティに広がれば広がるほど、個々の人びとの事情や背景は捨象される。のっぺらぼうのように一般的に語られる被災者や被害者の像やコミュニティは、コミュニティを構成するさまざまな社会関係や構造そのものから文脈や、現実にある政治性を消し去られ、ただ規範化された透明な理念として当事者たちに「降ってくる」。
本発表ではそのような当事者の中でも、母として、嫁として、娘として、そして女として、家庭内、コミュニティ、社会におけるケアの与え手として、あるいは未来の与え手としてみなされてきた女性たちに焦点をあてよう。ここでいうケアとは、育児、介助、医療、看護、介護、教育の領域にわたるものである。女性たちは、生きのびるために、そしてそれぞれの福利と自分が関わるケアの受け手の福利を求めて、現実には生々しくジェンダー化され、政治化された特定の文脈(しがらみ)の中に身を置きながら、「降ってくる」規範化された透明な理念としてのコミュニティ像に向き合わざるを得ないという、ひどく矛盾した状況にある。
そして、その像の中にひそかに含まれる、やはり脱文脈化・政治化され、規範化されたケアの概念と、それに付随する役割と肩書(本発表では母、嫁、娘などの家族関係の中におけるそれに限定したい)、それらを望ましいものとして歓迎する他者からの評価。それらに日々さらされながら、女性たちは、いつの間にか自分の肩に乗せられた自己決定と自己責任の重さに、つんのめりそうになりながら毎日を手さぐりで歩いている。そして、自由に選べない現実に諦念をもちつつも、何とか選択肢を増やそうと何かを失う覚悟を持って動き始めた女性たちも多い。
本発表では、母子避難家族やその支援団体に関する聞き書きや語りに関する社会学的な研究成果をもとに、女性たちが直面する構造化された選択肢の存在と、脱文脈化・政治化されたコミュニティとケアの概念がもたらす様々な困難や、福利の実現を目指して選択肢を生み出したり選んだりする自由からの疎外に焦点を当てて考えてみたい。
それにより、これまで語られてきた「ケアの倫理」とは違う観点から「生命の倫理」について思考することができるだろう。
【引用文献】
伊豫谷登士翁、斎藤純一、吉原直樹、2013『コミュニティを再考する』平凡社新書。
************
このワークショップを開催し、お二人にお願いした経緯について記しておきたい。私の躊躇を語ることになるが、それ自身、ワークショップを行うことの意義と狙いを側面から示していると考えるからである。
『年報』第62集への寄稿に記したように私は、会員の企画としてではなく、学会の企画としてワークショップを開催することを提案したが、「隗より初めよ」ということで、今年度は私の「応募」ということで開催の承認を頂いた。当初、私は、話題を限定するよりも、この震災に福島・宮城・岩手において直接的に関わった、会員外の、しかも、できれば「学者」ではない方の、いわば「生」の提題をお願いすべく試みたが、様々な事情から、仲介に入って頂いた方にお骨折りを頂いたにもかかわらず、果たすことができなかった。
昨年度の共通課題の実行委員であった金井・川本両会員からの示唆を頂き、むしろ、昨年度の全体テーマの継続であることを示し、その流れで話題を提供し、次年度に繋ぐ話題を頂ける方にお願いするのがいいのではないかということになり、急遽、福永・米田会員にお願いし、幸いにも快く了承を頂いた。結果的に、「歴史的なコンテクスト」(米田)「脱文脈化」(福永)という、一見、逆のように見える表現をキーワードとしながら、現在の(普遍性を標榜する)倫理のあり方についての「批判」の重要性と、それが「要求」に矮小化されてしまう危険性とを考えるための最適の提題者をえたと考えている。
昨年度の共通課題の実行委員、提題者、そして関連して開催されたワークショップ・主題別討議の提題者、さらには、それらへの出席者に、そしてもちろん、「あなた」にも何らかの形で参加して頂ければ幸いである。
関連資料
◆(関連論文)米田祐介「〈核災〉と〈いのち〉の選別」、金井淑子・竹内聖一編『ケアの始まる場所――哲学・倫理学・社会学・教育学からの11章』ナカニシヤ出版(2015年2月27日発行)★ワークショップでの発表を踏まえた論考★
※リンク先:執筆(発表)者の承諾のもと元原稿を補正してアーカイブ
◆(関連論文)米田祐介「フクシマとサガミハラが投げかけるもの―「生産性」の2010年代、事件後に人間の尊厳について語るということ―」『立正大学哲学会紀要』第15号(2020年3月発行)★発表後の展開が示された論考★
※リンク先:執筆(発表)者の承諾のもとテキストデータをアーカイブ
◆(当日資料)米田祐介「〈核災〉と〈いのち〉の選別――「選ばないことを選ぶこと」の危機――」