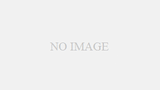〔アーカイブ・データ〕
・「第67回大会報告集」
・「会務報告」『倫理学年報』第66集(2017年3月30日発行)
第67回大会報告集
東日本大震災から見えてきたこと(4)
――5年目の「中仕切り」
実施責任者 高橋久一郎(千葉大学)
震災から五年が過ぎ、大会時には五年半となる。長い目で見れば「忘れる」ことは大事なことであると思う。しかし、「しばらく」は忘れてはならないことがある。
2011年の大震災との関わりで、そこに露わになった倫理学の問題について「生命の倫理」の可能性と重要性という全体テーマのもとにワークショップを開催してきた。昨年度まで三回にわたって「女こどもの倫理」という課題設定のもとに、子供を連れて「逃げた」母親たち、「留まった」母親たちが提示した問題を見てきた。必ずしも問題を「掘り下げ」たとは言えないが、継続のなかで見えてきたこともあった。他方では、残念ながら多くの人が「忘れてしまった、あるいは、忘れつつある」ということもまた感じないわけにはいかなかった。
そうした中で、「リスクと管理の論理」が強力に展開しつつある。実は、私自身は、この論理に「真っ向から反対」というわけではない。論理としてはむしろ理解しやすい。状況的にも、具体的な数値などについて三年前よりは格段に見ることができるようになっているから、こうした視点からのワークショップの開催も視野には入れている。
しかし、それだけに今年は、さらに先に進む前に、現時点での問題を確認し明らかにするために、2012年の大会の全体課題の問題意識を改めて振り返ってみたいと考え、大会時の提題者に、再提題をお願いした(残念ながら、もう一人の提題者であった鷲田清一会員は、「せんだいメディアテーク」館長の仕事と重なったため出席できないが、何らかの仕方で関わって頂こうと考えている)。
原発震災下の希望 福嶋 揚
1 原発震災発生から五年後に
原発震災は、日本全土におよぶ危機となって続いている。原子力非常事態宣言は解除されていない。日本列島上の人々は、どこにいようと、これから続く地震活性期を生き延びなければならない。その後もさらに廃炉作業という負の遺産を背負い、放射能汚染のなかで生き延びなければならない。
ここで筆者が問題としたいのは―四年前の倫理学会でのシンポジウムと同様に―人知の及ばぬ自然災害ではなく、人災としての原発震災、国家と電力会社がもたらした公害である。原発震災という産業事故は、戦後六十余年にわたって続いてきた―そしてすでにあらわになりはじめていた―日本社会の構造的な限界を炙り出した。それは資本主義経済と国民国家という、戦後日本を形成してきた二重構造の限界である。原発は、資本主義と国家権力の接点、あるいは核エネルギーの民事利用と軍事利用の接点をなしてきた。しかし原発の建設や稼働による経済成長が、もはや市民の平和的生存を犠牲にせずには維持できないことが、東日本大震災によってあらわになった。そればかりか、原発問題の背景にひそむ戦後日本国家の対米従属という問題も、米軍基地の問題と連動して、一層あらわになってきた1。
だが、このような問題や限界を認めまいとする否認の傾向が、根強く存在する。そのような勢力は、原発震災の危機的現状を隠蔽し忘却しようとし、それとともに従来の二重の構造(国家と資本の支配)をいっそう強化しようとしている。例えば原発の再稼働や輸出計画、汚染を隠蔽したオリンピック招聘、震災を奇貨とする独裁国家化(緊急事態条項の提案)といった、さまざまな出来事が相次いでいる。こうした一連の出来事は、近代的な国民主権から近代以前の国家主権への逆行現象をもたらそうとしている。
だが東日本大震災以降、こうした逆行現象だけではなく、そうはさせまいとする未来への志向も現れ始めた。それは、国家権力と資本主義経済という双頭の権力に対向し働きかける者たちの、多様な連携と運動である。国家と資本は、あたかも原発震災という教訓がなかったかのように、経済力と軍事力を追求し続けることによって、生態系破壊、格差拡大、さらに戦争へと突き進もうとしている。この自滅的なスパイラルを阻止するために、脱原発、資本主義とは異なる定常経済への移行、分権的で地域循環的な社会、さらに多種多様な平和運動が重要不可欠である。
2 神学的・倫理学的な希望
筆者は、キリスト教神学と倫理学という二つの分野にたずさわる。ここ数年の自らの研究や執筆、さらに社会運動の経験を拠り所として、原発震災という問題を考える以外にない。この間に筆者は『カール・バルト―破局のなかの希望』2を刊行し、ユルゲン・モルトマンの『希望の倫理』3を翻訳した。「希望」が関心の対象となってきたことは、「希望の神学」者であるモルトマンの学恩もさることながら、原発震災の衝撃なしにはありえなかった。絶望や諦念によって眠り込むことなく目覚めており、しかも堅固に耐え抜くことができるような「希望」は、どのようなものであろうか。
この間筆者にとって、「希望」概念を非神学的な歴史理解からも捉えるべきことが見えてきた。筆者はそのことを柄谷行人氏による最近のカール・バルト評価から学んだ4。「世界史の構造」の反復は、繰り返し未来を開示する。ユダヤ・キリスト教が伝統的に「神」として表象した終末論的地平は、現在を相対化し変革し続ける未来である。それは「まだない(noch nicht)」が「すでに今(schon jetzt)」あるという二重の性質をもって、現在に働きかけることを止めない、到来する未来である。
本発表においては、そのような「希望」を原発震災下において改めて探し求めたい。希望は、命と公正と平和が満ちる、まだ見ぬ未来への憧憬である。その未来は、義が満たされること、すなわち人災の責任の明確化、原状回復、賠償と救済、さらに脱原発(第二の原発震災の阻止)を含んでいる5。
1. 東日本大震災以後、原発問題と基地問題を対米従属という同じ根を持つものとして論じる様々な文献が出版されてきた。例えば石田雄『安保と原発―命を脅かす二つの聖域』(唯学書房、2012年)を参照。
2. 福嶋揚『カール・バルト―破局のなかの希望』、ぷねうま舎、2015年
3. 新教出版社より2016年秋に刊行予定。Jürgen Moltmann, Ethik der Hoffnung, Gütersloh 2010.
4. 福嶋揚「柄谷行人の交換様式論―『世界史の構造』の中のキリスト教」(ロ頭発表)、日本基督教学会関東支部会、於上智大学、2015年3月20日。この研究発表は、『現代思想』2015年1月臨時増刊号(青土社)の巻頭対談、柄谷行人・佐藤優「柄谷国家論を検討する―帝国と世界共和国の可能性」(8~29頁)に触発されたものである。
5. この点は、馬奈木厳太郎・白井聡「裁判で社会を変える―福島生業訴訟が問うもの」(『現代思想』2016年3月、青土社、118-139頁)から学んでいる。
「やましさ」をめぐる思考 宮野真生子(福岡大学)
5年前の「震災と倫理」で私が考えたかったことは、2つある。1つは「この災害に対して当事者でないものにどのような語りが可能なのか」ということ。そして、もう1つは「突然の別れをいかに受け入れていくことができるのか」ということである。これらに共通して言えるのは、生き残った者たちが抱えたある種の「やましさ」の問題である。5年前のシンポジウムで、前者に関しては、地震を日本の文化や伝統と結び付け、「無常」によって受け入れようとする、震災直後に多く見られた態度を批判した。たしかに日本的な無常感の伝統は、理由なき死を引き受ける絶好の語りとして機能する(cf.村上春樹カタルーニャ講演)。だが、それは、そこにあった多数の死の個別性を奪うことで、生き残ってしまった者が、そのやましさを感じることを軽減しているにすぎないのではないか。以上の批判をおこなった上で、いかにして生き残った者が個別の死と向き合うことができるのかを論じた。震災のなかで死の偶然性は際だったものとしてあらわれ、それゆえ生き残った者は「なぜ、私が生きているのか」と強くやましさを感じることも多かった。こうしたことを田辺元の「死者との実存協同」の思想から読み解くなかで、生死を分ける偶然性は、悲しみややましさの源であると同時に、裏面から見るなら、いま自分が生きていることの「有り-難さ」を開示するものであり、それはまさに死者との出会い直しを意味することを指摘した。それは、生き残った者がさまざまなレベルで抱えることになるやましさを引き受けることこそが、(当事者にとっては)死者や(非当事者にとっては)震災という出来事とつながる道であるという結論であった。
だが、「やましさ」は非当事者1にとって本当に震災という出来事とつながる道だったのだろうか。今回、震災から5年が過ぎた本ワークショップで、私は再び、震災をめぐる非当事者にとってのやましさの問題を考えたいと思う。この5年という時間のなかで、多くの当事者が抱えた感情はやましさとそれにどう対応していいのかわからない戸惑いだったと感じる。じっさいに揺れを経験したわけでも原発の問題をリアルに感じたわけではない。一方に自らが生きる普段の暮らしがあり、他方でテレビをつければ同じ国の人が未曾有の災害に巻き込まれたことを見る。そこで語られる「日本」や「われわれ」という言葉と、そのなかに自分は位置していない(位置しているのがおこがましいような)感覚。それゆえ、そんな人間が(まさに私が)「未曾有の災害」と書くこと自体が、嘘くさく僭越な気がする。高橋源一郎は、そうした知識人の配慮ある言葉を「防災服を着た言葉」と言った。けれど、一体私は何を語ることができるというのだろう。
何をしても「やましい」という感情がつきまとう八方ふさがりのような状態が非当事者のまわりには存在する。こうした感覚は、基本的にはおそらく「距離」ゆえである。だが一方で、それは単に遠いから「やましい」ということではない。そうであるならば、私たちはこの地球上で起こっているテロや災害のすべてに対して「やましい」と感じるはずだからである。距離がありながら、そこは私たちが暮らす同じ国であり、「われわれ」という呼びかけで括られる土地である。しかし、その「われわれ」のなかに自分たちは入っていない、というある種の疎外感が非当事者にはある。その疎外感が、やましさをさらに募らせる。だが、どうすることもできない。距離は如何ともすることのできないものであり、その意味でやましさは所与のもの(それゆえ偶然的なもの)だからだ。この疎外感とやましさの2つの感覚が重なりあうなかで、非当事者は少しずつ震災を語ることを避けるようになったのではないか。あるいは学生など若い世代に顕著に見られるように、ひとつの悲劇的な物語として歴史化し、涙しながら消費することでやましさを消し去ろうとしてきたのではないか。私は5年の前のシンポでやましさを抱えることでしか非当事者は震災とつながることはできないと指摘したが、結果的にそのやましさは震災との断絶を強くする方向に働いたのかもしれない。だとしたら、非当事者はこのやましさとどう向き合うべきだったのか。そもそも、このやましさは一体どういう種類の感覚なのか。今回のWSではこの問題について再度考えていきたいと思う。
1. 「非当事者」と言っても、そこにはいくつものレベルの違いがある。今回は、とくに西日本に暮らし、直接の影響を受けていない人々を想定している。
昨年度のワークショップへの案内の文言を(昨年そうしたように今年もまた一年度繰り下げて)繰り返しておこう。2012年度の大会の共通課題の実行委員や提題者だけでなく、関連して開催されたワークショップ・主題別討議の提題者、さらには三年前・二年前、そして昨年のこのワークショップに出席された方には、そしてもちろん、はじめての「あなた」にも参加して頂ければ幸いである。
会務報告(所収:『倫理学年報』第66集(2017年3月30日発行))
高橋久一郎
今年度は、震災から5年目ということもあり「中仕切り」として、12年度大会において震災を統一テーマとして開催された際の提題者であった福嶋揚会員と宮野真生子会員に現時点での問題の回顧と状況、そして展望について提題をお願いした。それぞれ、「原発」をめぐる問題であることが無視されつつある状況にあっての「原発震災下の希望」、そして、問題について語る人々の多くがなにがしか抱えてしまっているように見える「「やましさ」をめぐる思考」状況についてさまざまな論点が提示された。参加者は多くはなかったが、それだけにむしろ熱心にまた密度の高い議論を行い、それを踏まえて最後に来年度のテーマについても論じあった。