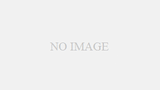〔アーカイブ・データ〕
・「第69回大会報告集」
・「会務報告」『倫理学年報』第68集(2019年3月30日発行)
第69回大会報告集
「東日本大震災から見えてきたこと(6)
――子どもの倫理(4)」
実施責任者:金井淑子、川本隆史、高橋久一郎
このワークショップはこれまで主として「女・こどもの倫理」という副題のもとに「東日本大震災」において、中でも「福島原発事故」との関わりで浮かび上がってきた問題を検討するために、一方では「避難」先での生活や福島の「現状」についての「事実」を確認するとともに、他方ではそうした「事実」を踏まえながら、この事故に向かう「倫理学」の立ち位置について意見を交換してきた。
今年度は、佐藤靜会員に放射能汚染における健康被害について、現状と倫理学からの応答のあり方について「女・こどもの観点」からの提題を頂くとともに、昨年度の横山道史氏の提題「倫理においてリスクを問題にすること」を引き継ぐ形で、世話人の一人である高橋が「リスク論」について考えるための材料を提供し、原発事故をめぐる「倫理」を語る「ことば」について論ずることとしたい。
母子避難に駆り立てたものとはなにか:水俣病・チェルノブイリ・優生思想
佐藤靜(大阪樟蔭女子大学)
二〇十一年三月十一日に起こった東日本大震災。それは単なる〈震災〉ではない。地震によって引き起こされた大津波、それが福島県沿岸にある東京電力福島第一原子力発電所の電源を停止させ、未曾有の大事故が起こった。そして、大量の放射性物質がばら撒かれた。私企業の利潤追求の結果というよりはむしろ、国策としての原子力推進政策の結果として生じた害であるがために〈公害〉であるといわれる。
放射性物質による被害、とりわけ低線量被曝の被害は、即座にあらわれるものではない。時間をかけて、数年後、数十年後にあらわれるものである。そうした影響が身体に及ぶことを怖れてなされたのがいわゆる「自主避難」である。それは、国からの指示によってなされた避難(年間積算線量二〇mSv以上の地域)とは異なり、避難区域に指定されていない地域住民が自らの判断によってした避難のことを指す。そしてその多くは母子避難という形をとっていた。
ではなぜ、母子避難であったのか。本報告では、ワークショップのテーマである「女こどもの倫理」という観点から、この問いを掘り下げることを試みたい。具体的には、二つの公害事件−−水俣病とチェルノブイリ−−をめぐる言説の検討を通じて、公害・環境問題の本質としての母子あるいは生殖をめぐるポリティクスと優生思想との関係を浮かび上がらせたい。
公害とは、環境問題でもある。では、環境問題とは何か。それは、環境が汚染され破壊されることである。空気や土や水のみならず、そこに生きる農作物や動植物、人間もまたその害を被る。そしてそれは、動植物や人間のいのちそのもののみならず、世代を超えたいのちのリレーに重篤な影響を与えるものである。現在の生命科学の技術水準においては、人は女から生まれるほかない。女という身体は、いのちが生まれ出づる場である。そうした厳然たる事実をこの世界に知らしめたのは、水俣病事件の受難者である胎児性水俣病患者たちの生のありようを通じてである。
水俣病という、人類にとっての未曾有の大惨事としか呼べないような事件、それは今も終わっていない。天の恵みである魚を食べた人たちは、その魚に含まれていた有機水銀によって体を蝕まれ、しびれや麻痺、感覚障害など様々な症状が出た。その苦痛は、今もなお続いている。また、その魚を食べていない人たち--胎児性水俣病、あるいは胎児性水俣病疑いと呼ばれる--も、母の胎盤を通過した有機水銀が体内に蓄積され、その影響による諸症状の只中にいる。水俣病の公式確認がなされたのは1956年、今から60年以上も前のことである。それだけの年月を経ても、今もなおそれは問題のままあり続けている。
もうひとつ重大な事件がある。それは、チェルノブイリ原発事故である。遠く離れた国での大惨事は、日本でも関心を持つ人々の手によってその実態が紹介され、そして日本でも女たちによる反原発運動が起こった。その運動を支える主張の主たるものは、放射能による植物の奇形や食品汚染、人体への影響である。そうしたリスクがあるから、原発はいけないという論理である。それに対して堤愛子は、そういった考えの陰にひそむ優生思想的側面の問題を障害者の立場から問題提起した〔堤1988〕。
本ワークショップは今年で六回目となる連続企画である。そのなかで、一つの論点となってきたことは、原発事故について語ることの難しさである。その難しさとは何か。それは、原発のリスクの算出それ自体というよりはむしろ、被害の実態あるいはこれから予見される事態を語る際に暗黙の前提とされる、「優生思想」という問題それ自体の語り難さではないのか。リスク管理といわれる時のリスクとは、単に人が傷つくことそれ自体だけではなく、障害あるいのちの出生をリスクと捉える優生思想なのではないか。こうした問いは、原発事故をめぐる議論にどう位置付けられるのか。二つの公害事件をめぐる議論を手がかりに、参加者との議論を通じてこの問いについて考えてみたい。
【主たる参考文献】
甘蔗珠恵子(2006)『まだ、まにあうのなら:私の書いたいちばん長い手紙(増補新版)』地湧社。
近藤和子・大橋由香子(2012)『福島原発事故と女たち:出会いをつなぐ』梨の木社。
堤愛子(1988)「ミュータントの危惧:甘蔗珠恵子『まだ、まにあうのなら』書評」『クリティーク12 特集 反原発、その射程』青弓社。
URL: http://www.geocities.jp/aichan822/myuutanntonokigu.htm(2018/7/13確認)
原田正純(2009)『宝子たち:胎児性水俣病に学んだ50年』弦書房。
マリーナ・ガムバロフほか(1989)『チェルノブイリは女たちを変えた』グルッペGAU訳、社会思想社。
リスクについて語ることの「倫理」
高橋久一郎
原発問題との関わりでリスク(あるいはコスト・ベネフイット)について語ることは、しばしば「倫理」を否定するとは言わないまでも、ある種の「偏向」のもとに語ることであると論じられることがある。背景には、三つのことがある。第一に、リスクが問題とされるさまざまな「出来事」・「行為」・「制度」にかかわる「事実」としてのリスクの大きさについての(「科学的」・「客観的」・「合理的」といった言い方で特徴づけられる)「判断」が難しいこと、同様にして、将来的に可能な複数の行為や制度を選択した場合の「比較」もまた極めて困難であるような問題であることである。第二に、これが直接的な理由であるように思われるが、多くの場合、そうした「判断」を全体として「統合」することは、「なしえないはずの」、あるいは、「なされてはならないはずの」とは言わないまでも、少なくとも極めて慎重に考慮されなければならないさまざまな「事実」についての「価値」的な「評価」を、一元化し、トレードオフできると暗黙のうちに認めて、特定の選択を(自らの「価値」意識のもとでのことであるにもかかわらず)「合理的なこと」「当然のこと」として論ずることになるように思われるからである。ここでは、「統合」に関してどのような「事実」を考慮するかの時点ですでに「主観性」が介在してしまう。実際、こうした場合には、どれほど慎重な考慮を試みたとしても、何らかの「偏見」抜きには評価の「統合」が「原理的に」不可能であるようにも思われるからである。つまり、われわれはさまざまな事実を評価し、ある種の観点からする価値について語ることを認めたとしても、それらをすべての人が同様に評価するとは限らず、また、それらの事実についてのさまざまな観点からする評価を統合するための、いわば「尺度の尺度(measure for measure)」が、具体的な「評価」の営みに先立つて「事前」にあるとは言えないからである。そして第三に、すでに触れてはいたが、明示的に言えば、これが根本にあるようにも思われるのだが、リスクの「評価」は単に「評価する」ためになされるのではなく、それに基づいてなされる「意志決定」、つまり、その後の(個別的な)「行為」や(社会的な)「制度」へと反映されることになるが、逆に、「評価」する者が事前に「望ましい」と考えている(一般的な)「行為」や「制度」のあり方が、(偏見がなかったならば)なされるべき「評価」、なしうる「評価」を歪めないとも限らないと思われるからである。
しかし、こうした「偏向」となりかねないという「評価」のあり方は、どのような立場をとろうとも、問題となっている「出来事」・「行為」・「制度」に関して「評価」をしようとする場合には、ある意味では不可避的に成立してしまうことである(ただし、この点を強調しすぎれば、「いまや原発問題におけるリスク論は「科学論争」であるより以上に「政治論争」である」といった、議論の現状についての、全く的外れではないとしても、第三者的な単なる「イデオロギー暴露」に堕しかねないところがある。それを試みようというわけではない)。われわれは暗黙のうちになにがしか、ある種の問題に関しては、ある種のリスクは考慮すべきではないリスクとするという仕方でリスクを考慮しながら「倫理」を語っている。そして、リスクについて語ることなしには「改善できない」とは言わないまでも、「よりよき選択」を断念することになりかねないということも、われわれがおかれている状況の一面として否定できないことのように思われる。そこで、ここに再び「価値」の問題が決定的な問題としてきわだってくる。しかも、ここでわれわれは、評価の「対立」ということが問題にはならない「たで食う虫も好き好き」の「価値相対主義」には立てないので、「価値評価の主観性」としてしばしば語られる論点、つまり、「評価の私物化」という問題をどのようにクリアするかが問題となる。
言うまでもないことだが、「公的機関」や「専門家」の「評価」が、直ちに、言葉の本来の意味での「権威」ある「評価」になるわけではない。「評価」を保証してくれる「尺度の尺度」を持たないわれわれが持っている道具は、ハーバーマス的に言えば「討議倫理学」ということになるのだろうが、要するに、プラトン以来の「知者」がいない状況での(「専門家」といえども「知者」ではないから)「問答法」による吟味である。とはいえ、今回のワークショップでは、具体的な、例えば年間10ミリシーベルト被爆についてなされた「リスク判断」についてのメタ「評価」といった試みをするわけではなく(私はその領域のいわゆる「専門家」ではなく、その「評価」の是非を「科学的」に論ずることはできない)、リスクをめぐる語りのあり方について、最近の代表的・典型的な議論を取り上げて、そこでの論じられ方の何が問題なのかを検討したい。
主として取り上げるのは、『しあわせになるための「福島差別」論』(本年1月刊)、その批判の論考をも含んだ『福島・被爆安全神話のワナ』(同6月刊)、そして、『福島事故後の原発の論点』(同6月刊)である。いずれも、いわゆる専門書ではなく「啓蒙」を狙いとした本であり、それぞれに批判も受けているようだが、現在の議論の「水準」を示していると思う。この際、特に注目し考えてみたいのは、これらの論を論じているのは「誰か?」という問題である。もちろん、それぞれの「著者(author)」であるわけだが、ホッブスに倣って言えば、彼(女)は、「本人(author)」であるだけでなく、誰かの「代理・代表(representative)」としての「人格(person)」でもある。誰の「代理」なのか?そして、さらにそれを論じよとしている「私」は?
なお、新に相応しい書籍が刊行された場合には、それも対象としたい。
会務報告(所収:『倫理学年報』第68集(2019年3月30日発行))
高橋久一郎
今年度は、佐藤靜会員が「母子避難に駆り立てたものとはなにか:水俣病・チェルノブイリ・優生思想」と題して、「女・こどもの観点」から継続的に現状と倫理学からの応答のあり方について、世話人の一人である高橋が「リスクについて語ることの「倫理」」と題して、昨年度の横山道史氏の提題「倫理においてリスクを問題にすること」を引き継ぐ形で、「公共的意志決定」における「リスク論」の歴史的背景と援用のあり方について論じ、原発事故をめぐる「倫理」を語る「ことば・論理」の対話のあり方の「困難」と「課題」について論じた。ここ三年ほど、三十名ほどの出席で推移しているが、学会員ではない方の参加がかなりあり、継続することの重要さを感じている。