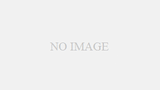〔アーカイブ・データ〕
・「第71回大会報告集」
・「会務報告」『倫理学年報』第70集(2021年3月30日発行)
第71回大会報告集
東日本大震災から見えてきたこと(8)
――女・子どもの倫理(6)――
実施責任者 金井淑子・川本隆史・(文責)高橋久一郎
このワークショップは、主として「女・子どもの倫理」という副題のもとに「東日本大震災」において、中でも「福島原発事故」との関わりで浮かび上がってきたさまざまな事象・問題について考えるために、福島の現状や「避難先」での生活についての「事実」を確認し、情報を共有するとともに、そうした「事実」を踏まえながら、この事故に関わる「倫理」のあり方、そして「倫理学」の立ち位置について意見を交換してきた。
この後、半年たらずで事故後10年を迎えようとしている今、ワークショップを振りかえって見るならば、熊本・愛媛の大会では九州の地に避難された方々の生活状況や四方原発、弘前では廃棄処理場、そして山口では中断こそしているが、取りやめになったわけではない)上関原発建設をめぐる状況などについて、「女・子ども」という視点からのレポートをお願いし、事実を見てきた。
今回は、福島の「現状」について、そこでの活動について、実際に関わっている星野勝弥氏を迎えてレポートいただくことをプログラムのメインとした。現在、「新型コロナ」の影響で、さまざまな活動に制約がある(大会そのものの開催も危ぶまれる)中での大会ということもあって、その中で、忙しい中貴重な時間を割いてレポートいただけることに世話人としては感謝し、みなさまの参会をお願いしたい。
(福島(原発地帯)の状況について、二点だけ確認しておけば、1)「帰還困難区域」は未だ東京23区の半分ほどに縮小したが、当初の避難指示区域の7万人弱の住民登録者のうち、居住しているのは3割弱、65歳以上の高齢化率は4割強である。2)「復興・創生」に関する10年の時限措置が今年度で終了することもあって、いわゆる「かけ込み」でのインフラ・建設などが急速に進んでいる。その中には、例えば、「復興・廃炉工事」や「Jビレッジやロボット研究拠点など」を顧客とするホテルの建設なども含まれている。)
さて、ここからは「さん」付けにさせていただくが、星野勝弥さんについて紹介したい。通常ならご本人からの「発表要旨」を掲載するところであるが、星野さんは今、原発事故と新型コロナ禍のもとで「訪問看護ステーション」の立ち上げという仕事に関わり、最後の詰めの段階にある。大会が無事開催されたならば、福島の状況について、星野さんの作業を含めてお話しいただくよう、無理をおしての出席と提題のお願いをしている。
星野さんは現在67歳、牧師をしていた親の元に生まれ、東京大学に進学したが、「キリスト教から離れたい」との思いから休学、日雇い仕事などする日々を送った後、高等学校で国語を教える身となった。
30歳を過ぎてから、キリスト者としての母の活動や近所の女性医師の仕事を見ているうちに、医療・介護の仕事への従事を志したが、「子どもが自立するまでは」というパートナーの言葉に思いとどまり、10年ほどして、長男の大学進学を機に、高校を退職、55歳だった。
大学の看護学科に入学し、看護師・保健師の資格を得て、59歳で都内の病院に勤務、訪問看護の仕事で経験を重ねながら、「原発事故」後、福島に通い始めた。原発立地自治体ではなく、その恩恵も少なかったにもかかわらず大きな被害を受け、避難を強いられた「飯館村」である。
17年の10月、東京にパートナーを残して、看護師と手ためた貯金をつぎ込んで中古住宅を購入し、「単身赴任」し、村の「包括支援センター」で保健師として働らき始めた。16年9月から村の唯一の診療所「いいたてクリニック」は再開されていたが、週二日午前中だけの診療という状況を見て、「訪問看護が必要だ」との思いからだった。
避難指示は原発に近い南部の長泥地区を除く村の大半の地域で17年3月末に解除されたが、帰還は進まない。とりわけ、いわゆる「現役世代」の帰還は進まず、高齢化が進んでいる。解除後、三年三ヶ月ほどたったが、帰還したのは、漸減する住民登録者の3割弱で、その6割近くが65歳以上である。
そんな中で、この6月には法人登録がすみ、「訪問看護ステーション」としての活動を始めようとしている。施設は、キリスト教の「(無償の)愛」を意味するギリシア語の「アガペー」と酪農の村だったことにちなんで「べこ(牛)」を組み合わせて、「あがべこ」と名づけたとのことである。星野さんにとっては、キリスト教との対話を両親とは別の仕方で果たすことにもなる。この対話がどのように展開することになろうとしているかも、活動にどのように関わり影響しようとしているかといった点も伺いたいところである。
星野さんのキリスト教との関わりを強調するような紹介となったが、そこに「覗き趣味」的なところが全くないわけではないが、それが主眼ではない。星野さんのお話を中心にワークショップを行うことの狙いを確認する形で記しておきたい。実施責任者としての私たちが心がけてきたことの一つは、さまざまな状況の下でそれぞれに事故後に向き合っている一人一人の活動と考え方を、安易に普遍化して「結論もどき」を出さないということであった。さまざまな場所や抱えている問題、そして一人一人の立場に関して理解しやすいこと、それらの共通性を纏め上げるという仕方での、言葉での「普遍化」は、倫理学を(敢えて言うが)「生業」としてきた者たちにとっては、ある意味で楽な作業である。しかし、これまでのワークショップを通じて試みてきたことは、そこにはない。そうではなくて、倫理学に携わる者が、敢えて言えば、倫理学の視点からではなく、「見る」こと、そして、「見る」ことの意味を、改めて考えてみることにあった。
当初「女・子ども」という視点設定は、あえて「女・子ども」という言い方をしたわけだが、ある種の「差別」を内包しかねないことを危惧した。「普遍化」しえない、(積極的な言い方をすれば、最終的には)してはならない視点からの言葉を語ろうという企画だったからである。しかし、今、日本の状況を考えるならば、この視点設定は、残念ながら、一層重要になっているのではないかと考えている。「自由」や「正義」といった、倫理の「普遍性」を語る「理念」が、「普遍性」の名の下に「特定の人々の利益の保護」のための「道具」に化しているように思われることがしばしば生じているからである。今回の新型コロナをめぐる「対策」においても、すべての「住民登録者」への「世帯主」を通じての「特別定額給付金」という、それ自体としても問題のある仕組みではあるが、それに隠れる形で、株価維持のために、それに倍する資金が「日銀」を通じて多くの「市民」には見えない形で投入されている。こうした資金の恩恵に与るごく一部の企業が「社会」への(いわゆる「メセナ」などの、近年すっかり冷めてしまったように見える活動を否定するものではないが)「貢献」ではなく、「株主」への利益をその第一の「存在理由」とする以上、こうした資金投入は、その投入をさらに正当化する、いわゆる「実体経済」の活性化に向けての有効性についての説明抜きには、ただの「偏った利益分配」である。それは、言いかえれば、確かに強力であり、社会の多くを覆ってはいるが、現代といえども普遍化してはいない資本を普遍とする論理でしかない。「資本の普遍性」は、「女・子ども」はもとより、「資本」に参加できない「老人」さらには、いわゆる「マイノリティー」をも排除する、「(成年)男性」を、敢えて言うが、強引に普遍化したシステムでしかない。「自由」や「正義」が、あるいは「誤って」、また「不当にも」、そうしたシステムを支えるための「道具」として使われているなら、それが「誤っていること、不当であること」は、それに預かっていない者の視点から語る他はない。その中に、「女・子ども」がいる。
倫理の、いわゆる「普遍性」は、「正義」や「自由」「平等」、そして「権利」といった「理念」の普遍性によって予め担保されているわけではない。それらの「理念」自体が、さまざまな「異義申し立て」との対話を通じて、歴史の中で獲得され鍛えられてきたとはいえ「未完の道具」であり、「普遍性」を担うあり方へと「改訂」されるべき「踏み台」でしかない。
星野さんは、「女・子ども」ではないが、(失礼にはならないと思うが、などと附加してしまうことが問題だと言われそうだが)「老人」である。もちろん、星野さんが「老人」を代表するわけではないし、「老人」という「枠」を設定すること自体が、再び問題であることも確かだが、これまで福島で活動し、今新たな試みを始めようとしている星野さんが一人の「老人」として、そして、「人間」として語る言葉として聞き、対話したいと思う。
もう一つの提題は、実施責任者の一人高橋が、今回の新型コロナ禍においても繰り返されたというか、原発に続いて二度目であるにもかかわらず、より問題含みな展開を示しつつあるように思われる「科学の知見と政治の決定」の関わり合いについて、時系列的な経緯をレポートしたい。
会務報告(所収:『倫理学年報』第70集(2021年3月30日発行))
高橋久一郎
このワークショップは、主として「女・子どもの倫理」という副題のもとに「東日本大震災」において、中でも「福島原発事故」との関わりで浮かび上がってきたさまざまな事象・問題について、福島の現状や「避難先」での生活についての、「事実」を確認し、そうした「事実」を踏まえながら、この事故に関わる「倫理」のあり方、「倫理学」の立ち位置について意見を交換してきた。
今回は、福島の「現状」について、さまざまな問題を孕んだ「帰還政策」が進められる中で、新たに「訪問看護ステーション」を立ち上げた星野勝弥氏のレポートをプログラムのメインとした。星野氏の目標と、現場での「齟齬」というのではないとしても、活動の中で生じた問題について報告いただき、かなり立ち入ったディスカッションを交わすことになった。また、来年度は震災から10年が過ぎた時点での開催となることから、ワークショップのあり方についての提案などもいただいた。
Zoomでの開催となったが、例年よりも多く60名ほどの参会をえたことに感謝したい。