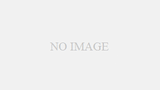〔アーカイブ・データ〕
・「第72回大会報告集」
・「会務報告」『倫理学年報』第71集(2022年3月30日発行)
・(当日資料)渡部純「原発事故と教育の危機―ハンナ・アーレントの「教育の危機」から考える―」
第72回大会報告集
東日本大震災から見えて来たこと(九)――女・子どもの倫理 (7):「十年が過ぎた時点で」
実施責任者(金井淑子・川本隆史・高橋久一郎)
本ワークショップは、東日本大震災の年の第61回大会で急遽開催された「特別企画」と翌年の「共通課題震災と倫理」と「主題別討議原発事故について倫理学は何が言えるか」を承ける形で、「原発事故」の孕む事実的・倫理的問題の大きさに鑑み、「対話」の機会を継続的に持つことを狙いとして、「共通課題」の実行委員を努めた三名が「実施責任者」として第63回大会より企画してきた。
今回は、当初、震災から10年目を「区切り」とした「ミニ・シンポジウム」の開催も考えた。しかし、「帰還」政策が進められ「復興・創生」を謳った時限措置も終了し、「終結」ムードが作られているが、「終結」とはほど遠い状況にある中では、ここで「区切り」を示すこと自体が「終結」ムードに棹さすことにもなりかねないことから、むしろ初心に帰るべく、福島の県立高等学校で教育にあたっている渡部純氏に福島での「教育」の現状についてレポートいただき、さらに、教育のあり方についても考える企画とした。
原発事故と教育の危機―ハンナ・アーレント「教育の危機」から考える―要旨
渡部純(福島東高等学校)
東電福島第一原発事故(以下、「原発事故」とする)発災から10年目の今年、安倍晋三首相が福島第一原発の状況を「アンダーコントロール」と騙って招致された東京大会が、「復興五輪」を掲げながらコロナ禍のなかで開催される。だが、現実は、今もなお原子力緊急事態宣言が解除されておらず、福島県内外に35,191人の避難者が存在している(2021年6月8日,福島県発表)。しかも、自主避難者に至ってはこの数字に含まれないまま行政に黙殺され続けている。原発事故で生じた汚染土や廃棄物はおろか、そもそも原発から出る放射性廃棄物の最終処分地もいまだ確定していない。そして、第一原発内に溜まり続ける「処理水」は、トリチウムを除去する技術がないまま海洋放出することが政治決定され、40年以上にわたるとされる福島第一・第二原発の廃炉作業は、次世代に委ねざるを得なくなってしまった。これら未決の問題を先送りしながら、原発事故の「アンダーコントロール」や「復興」を僭称することは政治の欺瞞でしかない。
原発とは技術的解決の見通しが立たないまま、それによって生じる負債を未来へ先送りし続けることでしか機能しない無責任体系のことである。そこにおいて先行世代が次世代に負う責任とは何か。その伝達はいかにして可能なのか。今回のワークショップで問いたいことはこのことであり、それはとりもなおさず教育という営みに深く関わる。
筆者は福島県立高校の教員であるが、今の生徒たちが被災当事者であるにもかかわらず、そのときのことをほとんど覚えていないという声を耳にするにつけて、次世代にあの出来事の記憶や教訓を伝達することが困難な時期にきていると感じている。しかし、この間、被災地では「学習」の主体たる子どもを通じて原発や放射線をめぐる「教育の政治化」が為されてきたことを無視するわけにはいかない。
2011年8月、事故収束の目途も立たず放射線被ばくが懸念されるその時期に、福島県において全国高等学校総合文化祭の開催が強行された。そのイベントにおいて福島の高校生が次のメッセージを表明している。「福島に生まれて、福島で育って、福島で働いて、福島で結婚して、福島で子どもを産んで、福島で子どもを育てて、福島で孫を見て、福島でひ孫を見て、福島で最後を過ごす。それが私の夢なのです。あなたが福島を大好きになれば幸せです」1。そのひと月後、野田佳彦首相がこの言葉を所信表明に引用しながら、「こうした若い情熱の中に、被災地と福島の復興を確信できるのではないでしょうか」と演説した。福島県教育委員会教育長の鈴木淳一は、この言葉を教育再生実行会議(2018年度)で引用し、「福島に生き、福島を復興させようと懸命に考えている高校生がいる。その考えに正面から向き合い、復興教育を進めることが福島県の希望そのもの」と掲げた2。
原発事故さえなければ当たり前に享受できたであろう福島での生活を「夢」と形容せざるを得なくなった高校生の言葉には、あらためて原発を受け入れてきた世代として責任の重さを痛感する。しかし、ひとたび政治がこの高校生の言葉に被災地の「復興」を代表させるとき、その「夢」に当てはまらない生き方を排除する政治力学がはたらいていることを看過すべきではないだろう。今日、被災地では「復興」という未来へ推し進める政治的な力が強くはたらいているが、それは原発事故の被害が過去として過ぎ去っていない人々にとっては暴力的でさえある。しかし、そうであるがゆえに、政治はその批判をかわす役目を子どもに被けてこなかっただろうか。
首相官邸ホームページでは、現状において福島の原発事故での外部・内部被ばくが住民の健康に影響を与えるとは考えにくいとの見解が示されつつ、それを裏づける事例として、福島県立福島高等学校の生徒たちが国際高校生放射線防護会議(2015年3月、フランス)において発表した放射線量の比較研究が紹介されている3。福島県と他県及び外国でうける外部線量の間に差はないという高校生の研究成果は、広くメディアでも取り上げられた。この学習指導に当たった原尚志教諭は、その意義について「原発事故直後から、放射線の影響を懸念するニュースは度々取り上げられたが、6年の間に様々なデータが蓄積され影響を否定する結果が公表されているのに、メディアが取り上げない。それは私たちにとって、正確な情報を獲得する機会を奪われていることを意味する。特に将来を担う若い世代に放射線や福島の状況を正しく伝え、彼らの不安を取り除くことは,福島への信頼を回復する上で大切なことではないだろうか」と述べている4。
なるほど、原発事故以来、科学的事実にもとづかない「風評被害」が福島の人々を苦しめているという言説は、福島への差別に反対する立場からも主張されている5。今年の3月には、原子放射線の影響に関する国連科学委員会が、これまで福島県民に被ばくの影響によるがんの増加は報告されておらず、「今後もがんの増加が確認される可能性は低い」との評価を発表した6。だが、放射影響に関する事実をめぐっては、いまだ科学論争を背景にした政治的意見の対立が解消されたとは言いがたい。
たとえば、福島県は原発事故時に18歳以下だった子どもに対する甲状腺がん検査を継続し、2020年6月末時点で202人が甲状腺がん診断を受けたと発表しているが、この結果をめぐっては医学的な専門家からも対立する見解が表明されている。その一方は、過剰診断の危険性を指摘しながら甲状腺がん検査の継続は正当化されないとする緑川早苗などの立場であり7、他方は「検査は早期発見・早期治療に役立っており、縮小ではなく継続・充実化を図ってほしい」8との要望書を福島県に提出した、崎山比早子が代表を務めるNPO法人3・11甲状腺がん子ども基金などの立場が挙げられる。つまり、甲状腺がん検査の継続という問題一つをとってみても、原発や放射線問題は今なお政治的に争われている実態があると言わざるを得ない。
だが、ここで問いたいことはそのいずれかの正否ではない。むしろ、なぜいまだ科学的かつ政治的な議論の紛糾が継続する中に、「正確な情報」の伝達として高校生の学習活動を代表させるのかということである。言い換えれば、子どもを政治の世界に晒すことの弊害を問いたいのである。野田首相と鈴木教育長の発言に関しても、いまだ原発事故で汚染された故郷への帰還を迷う被災者がいるなかで、高校生の言葉を復興政策の例に挙げるのか。そこに子どもを盾にして反対意見を封じる意図がないと言い切れるだろうか。
それに関してハンナ・アーレントが「教育の危機」において、子どもという存在を大人の世界である公的領域に晒すことの危険性について論じたことが注目される。アーレントは「隠れることによってのみ生育できるものと、公的世界の全き光のもとにすべてをさらす必要のあるもの」9との区別を捨て去った近代社会では、子どもが成長するための条件が破壊されていると論じたが、この批判的視線は彼女自身が論争に巻き込またリトルロック事件の問題にも結びついている。
リトルロック事件は、黒人差別撤廃政策の一環として黒人と白人の統合教育を高校に導入したことで政治闘争が起きた事件であるが、アーレントはその公民権運動の戦術に対し、「成人ではなく子どもたちに責任を転嫁するものであり、極めて不公正なもの」と批判している10。なぜならば、「子どもは、妨げられることなく成熟するために、安全な隠れ場所を本性上必要とする」からであり11、その意味で政治的領域に晒すべきではないのである。「どの子どもにもある新しく革命的なもののために、教育は保守的でなければならない」が12、しかし「現状を維持しようとするこの保守的な態度は、政治においては破壊しかもたらさない」13。この両者の相反する論理を混同し、一方が他方に手段化されるとき、子どもの本性たる「革命性」は失われてしまう。その意味で原発事故後の「教育の政治化」とは、まさにこの教育の危機そのものということになるだろう。
帰還困難区域が多くを占める双葉郡の教育復興の拠点として、2015年に開校したふたば未来学園高校は、その建学の精神を「変革者たれ」としている。それについて同校の丹野純一校長(当時)は、「自分自身を変える。地域を変え、社会も変える。一人一人ステージはばらばらでも、それぞれの場所で変革を起こしていく。そんな創造者が必ず出てきます」と語っている14。過酷な被災地域の人材を育成する使命感が伝わる言葉である。しかし、他方で福島民友新聞記事に記述されたように、その創立の起源に「住民帰還の呼び水にしようと郡内8町村の教育長らによる中高一貫校設置構想から生まれた学校」15という政治的企てがあったとすれば、次のアーレントの言葉はどのように響くだろうか。
いまや大人ではなく、子どもたちに世界を変革し、改善することを求める時代になったのだろうか。そしてわたしたちは政治的な闘いを、校庭で闘わせようというのだろうか16。
以上の問題意識から本ワークショップでは、このアーレントの教育思想を手がかりに、原発事故後の教育の危機と可能性について参加者の皆さんとともに考えるものとしたい。
- 2011年8月4日「ふくしま総文」総合開会式・構成劇「ふくしまからのメッセージ」より。 ↩︎
- 鈴木淳一「福島県の高等学校における創造的復興教育」,首相官邸・教育再生実行会議(高校改革WG),2018年年8月28日,(URL:https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/jikkoukaigi_wg/kaikaku_wg1/siryou5-1.pdf 2021年7月15日確認) ↩︎
- 首相官邸ホームページ、遠藤啓吾「放射線の健康影響~「風評被害」について再び、福島の高校生のフランスでの発表~」(URL:https://www.kantei.go.jp/saigai/senmonka_g81.html 2021年7月15日確認) ↩︎
- 原尚志「福島高校の放射線の教育」、日本原子力学会誌「ATOMOΣ」第60巻、2018年(URL:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaesjb/60/1/60_7/_pdf/-char/ja 2021年7月15日確認) ↩︎
- たとえば、池田香代子・開沼博ほか『しあわせになるための「福島差別」論』、かもがわ出版、2018年参照。 ↩︎
- 朝日新聞、2021年3月9日付記事。 ↩︎
- 緑川早苗「現在の福島では甲状腺検査を継続することは正当化されない見直しを行わない『不作為」がもたらすもの」2021年3月8日、ウェブ論座。(URL:https://webronza.asahi.com/national/articles/2021030100012.html 2021年7月15日確認) ↩︎
- 『週刊金曜日』2021年6月18日付記事。(URL:https://news.yahoo.co.jp/articles/d328a445b28a1a243d181bba268b958a82168933 2021年7月15日確認) ↩︎
- ハンナ・アーレント「教育の危機」,『過去と未来の間――政治思想への八試論』、引田隆也・齋藤純一訳、みすず書房、1994年、253頁。 ↩︎
- アーレント「リトルロックについて考える」,『責任と判断』,中山元訳,ちくま学芸文庫,2016年,361頁。 ↩︎
- 前掲「教育の危機」,253頁。 ↩︎
- 同前,259頁。 ↩︎
- 同前,259頁。 ↩︎
- 朝日新聞,2017年3月10日付記事,「インタビュー・子どもの心の復興」,参照。(URL:https://digital.asahi.com/articles/DA3S12834029.html?iref=pc_ss_date_article 2021年7月15日確認) ↩︎
- 福島民友新聞,2021年3月5日付記事。https://www.miny-unet.com/news/sinsai/serial/10/05/FM20210305-591406.php ↩︎
- 前掲「リトルロックについて考える」,375頁。 ↩︎
なお、福島に関わる一般的な直近の事実情報については、高橋が紹介する予定です 。会員・非会員のみなさまの参加をお待ちしています。(文責 高橋)
関連資料
◆(当日資料)渡部純「原発事故と教育の危機―ハンナ・アーレントの「教育の危機」から考える―」
会務報告(所収:『倫理学年報』第71集(2022年3月30日発行))
高橋久一郎
福島県の県立高校で教育に携わっている渡部純氏に「原発事故と教育の危機」というタイトルで福島における教育の現状と問題点についての提題を項き、さらに関連する事例報告を会場から伺った後で、三十名ほどの出席者と共に主に二つの論点について討論した。一つは、教育における「権威」をどう考えるかという一般的問題を背景としつつ、アーレントの議論を承ける形で、児童・生徒の「保護と成長」という教育の目的についての理論的問題点である。もう一つは、「復興」という旗のもとでの、例えば「高校生「語り部」事業」といった「教育の政冶化」の事例と問題点、また全国に潜在する「隠れ避難者」どころか、福島における「隠れ帰還者」が生じているといった状況、そして、そうした避難者・帰還者の連携についての現状と問題点についてである。さら、来年度のテーマについての意見も伺った。