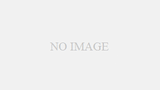〔アーカイブ・データ〕
・「第73回大会報告集」
・「会務報告」『倫理学年報』第72集(2023年3月30日発行)
第73回大会報告集
実施責任者 金井淑子
実施責任者 川本隆史
実施責任者 高橋久一郎
山本剛史
東日本大震災から見えて来たこと(十)
一昔前の話しではない
今回は、ワークショップとしては十回目である。当初、「ミニ・シンポジウム」のような形態で、ある種の「中仕切り(summing up)」のような機会とすることを考えていたが、「中仕切り」できるほどにも「事故」は終わってはいない。この五月から、福島原発事故との関わりで議論されている「甲状腺ガン」の問題について、裁判が始まった。さらに七月には、「株主代表訴訟」の判決も出たばかりである。「事故」についての事実と責任の解明と検証は、むしろこれからである。
これから十一月以降、本格的な裁判過程に入る「甲状腺ガン」の問題を中心に、これまでの経緯や論争状況についての「事実」を確認し、その上で、これからの展開を含めて、この問題と「私たち」の関わり合いについてどのように考えることができるかについて、山本剛史会員の報告をもとにディスカッションしたい。
現在、山本会員は、福島原発事故との関わりで、「対話を通して被災者や当事者が培ってきた様々な知恵を掘り起こし、…環境倫理学理論と突き合わせて、広く共有可能な思想として発信する」試みを「環境倫理学と民衆に根差す思想の応答」という研究課題のもとに行ない、成果を纏めているところである。
[提題]福島第一原子力発電所破局事故から11年、倫理学の課題
山本剛史
はじめに
去る2022年7月13日、東京電力が福島第一原子力発電所の津波対策を怠ったがゆえに、東日本大震災とそれに伴う大津波で大事故が引き起こされたとして、株主が当時の経営陣に対して損害賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は被告である元会長以下4名に対し、計13兆3210億円もの支払いを命じる判決を下した。またこれに先立つ1月27日には、事故当時福島県内に住んでいた男女6人が、小児甲状腺がんを発症したのは福島第一原発事故で放出された放射性物質に被ばくしたためであるとして、東京電力に損害賠償を求めて提訴している。
他にも、今なお係争中のもの、結審したものを合せて、被災者が東京電力や国の責任を問うた数多くの裁判がある。それらの口頭弁論の準備書面のいくつかを読み、被害の深刻さを見て取ることは容易であるし、原発事故そのものが現在も継続していることを思い知らされる。
リスクの科学的合理性と社会的合理性
原発がもたらすリスクは多様であるだけではない。原発から発する放射性物質は五感で感知できないので、ウルリヒ・ベックのリスク社会学が指摘するように、計測によって把握しなければならない。計測するためには科学的知識が必要である。また、計測した値を安全か、危険か評価する基準は一見純粋に科学的で、それゆえに客観的であるように思えるが、ベックによると実は基準自体に社会的な価値観、すなわち評価する者の価値観が必ず反映される。そうであってみれば、リスクをだれが評価するのか、評価の権限をだれが握っているのか、が重要になる。ベックのリスク社会学は、科学的工学的に数値化されるリスクと生活や人間関係の変容に関する数値化しえないリスクとの2種類があるというより、一見人間的な価値評価を免れているようなリスクの議論においても人間的な価値評価を抜きにすることができないのだと指摘する。つまり、リスクの評価や受け入れは科学的合理性のみならず、社会的合理性も尺度とするのである。
小児甲状腺がん患者を追い詰める構造
ところで、小児甲状腺がんの発症率は通常であれば日本国内でも欧米でも10万人あたり0.2人であるとされていたのに対し、原発事故を受けて開始された福島県県民健康調査とその調査外の最新の集計では、合計301人が甲状腺がんの疑いがあると診断され、そのうち226名が癌と確定した。政府はこうした小児甲状腺がん患者と原発事故との因果関係は科学的に見てないという見解である。そのような見方は、UNSCEARやIAEA、ICRP等の報告書に基づくものとしている。ベックの言葉遣いで言うなら、政府はUNSCEAR等のお墨付きを通して科学的合理性を確保すると同時に、自動的に社会的合理性も確保していると認識し、また主張している。
しかし日本政府の政策が科学的合理性を有するか、という点ですでに大きな疑念がある。小児甲状腺がんと福島原発事故の因果関係の有無を調べる基本データとなるはずの初期被曝量が、1080人分の計測値しか記録されていない事はよく知られている。にも拘らず、甲状腺等価線量で100m㏜(被ばくによる確定的影響が出る下限値とされる値)以上被ばくした人はいないと言い切れるのだろうか。30万人以上が甲状腺の測定を受けたとされるチェルノブイリ原発事故と比べて、データが少なすぎるのではないか。新聞記者の榊原崇仁は、実は事故当時甲状腺に100m㏜を超える被ばくをした可能性の高い子供がいることを政府が調査の過程で発見していたことや、福島県内のスクリーニング会場で計測値の記録が残されなかった経緯を調査して報告している。それでも、この1080人分の計測値に基づいて、チェルノブイリ事故と比べて甲状腺被ばくの量は少なかった、と言われているのである。
低線量被ばくのリスクは原理的に不確実なものであるが、だからと言ってデータの不足は市民の判断の妨げになる。この問題に患者ないし一般市民にとっての社会的合理性が成り立つとするなら、それは一つには、充実したデータが市民に公開され、それに基づいて当事者自身の自己決定と、当事者の意見の社会への反映が可能であるという状況であろう。
6名の小児甲状腺がん患者の原告からは、政府による科学的合理性の強弁を通して、被ばくの心配はしなくてもよいという社会的合理性が形成され、自らの苦しみが非合理であると認識せざるを得ずに、開示することを避けて個々で抱え込んでいるという構造が浮かび上がる。
内部被ばくの危険性を定めるのは誰か?
また、内部被ばくに関わる食物中の放射線物質について、100㏃/㎏以下であれば流通を妨げないと国は定めている。福島県内の多くの自治体では、食品等の検査も行っており、その際の放射性物質の検出下限値は100㏃/㎏よりも低く設定され、例えば郡山市ではセシウム137と134の合計で大体8から18㏃/kgの間に下限値を設定し、いずれの食品も「不検出」となっている。「不検出」とは、放射性セシウムが含まれていないという意味ではなく、検出下限値を下回っているという意味である。しかし、「不検出」と示されることで「安全」であると直感される可能性が出てくる。従って、「検出下限値」を政府行政がどのラインに設定するかという所で、市民が得る知識自体が結局権力構造の枠において規定されていて、やはり一般市民は自分たちで低線量被ばくのリスクをコントロールするための知識を充分には得られない状況へと追い込まれている。
総じて、原発事故以後11年間にわたって、日本国民は多重的な無知の状態に置かれているのではないだろうか。原発事故により放出された放射性物質に、誰が、どこで、どの程度晒されたのか、もしくは現在も晒されているのか(食料等による内部被ばくの問題を含む)についても当事者が充分に知らされていない。少なくとも知らされていないのではないかという疑念を持っている人は少なからずいる。
「最適化」原則と健康権
筆者は、この5~6年来、幾人かの福島原発事故被災者の方々からお話を伺ってきた。こうした人たちは、リスクに関する知識を規定する側と知識を受け取る側との間に権力勾配が生じ、構造的に無知の状態に留め置かれている事をそれぞれの現在の生活の中で骨身に沁みて感じている。その中でも、例えば認定NPO法人いわき放射市民測定室「たらちね」は、目に見えない放射能リスクを自ら測定することで可視化し、自分たち自身で知ることができる事に気づいた人たちのグループである。「たらちね」では、持ちこまれた食物、土壌、あるいは第一原発沖合の海水等の放射線量を測定するのだが、その際の検出下限値をγ線の場合1㏃/kgか、それよりもさらに低く設定している。そうすることによって、各自治体の計測よりも微量の放射線を検出することができる。さらに、甲状腺がん検診も独自に行っており、県民健康調査では検査の時には何も教えてもらえず、後日結果が記された紙が郵送されてくるだけなのに対し、「たらちね」ではエコー検査をしながらその場で結果が医師によって丁寧に説明されるのだという。
「たらちね」は、低線量被ばくの恐れのある土地で生き続けるために必要な知識を自らの手で獲得し、それによって自らにとって合理的な判断と行動を可能ならしめようとしている。すなわち、科学的合理性と社会的合理性とを独自に獲得しようとする試みである。行政とこの市民組織との合理性をめぐる対立は、実は放射線と生命との対立でもある。
ICRPは最新の2020年勧告(=刊行物146)に至るまで、一貫して被ばくリスクそのものとリスク回避の経済的社会的合理性との間のバランスを「最適化」することを放射線防護の原則として置いている。これに対し、「たらちね」をはじめ皆、事故に由来する放射性物質からの低線量被ばくを生きること自体との対立と見なし、できる限り放射線量を下げる事、下げられない土地でリスクを最適化しながら生きる事を間接的に強いられない事を是としている。これは、いわゆる「グローバー勧告」の指摘にも沿うものである。
「最適化」原則ではなく、グローバー勧告が言うところの「健康に対する権利」を尊重するためには、科学的合理性と社会的合理性の双方が被災当事者をはじめとする国民に広く開かれていなければならない。そのうえで、「たらちね」のような市民組織が行政の仕事をクロスチェックする形が望ましいと考えられる。
環境倫理学、あるいは倫理学の方法と課題
今回の報告の土台となっているのは、ただひたすら震災と原発事故の被害について被災当事者の方々に教えを乞う事である。話を聞いて初めて分かったことはたくさんあるが、原発事故問題を含む環境倫理学でも、利益相反の問題が非常に重要であることが分かってきた。「たらちね」は多額の活動資金を会員費やクラウドファンディングで賄い続けている。似たような趣旨を掲げる団体は他にもあるが、仮に活動を成り立たせる収入が原子力産業と関連する所から出ていたなら、どうしても東電や「最適化」原則に従い帰還政策を推進する行政を相対化する主張や行動をしにくい。このような構造に着目しない倫理学は構造的な無知をむしろ強化する役割を自覚せずとも果たすだろう。
ベックは、リスクとベネフィットの配分の不公正が問題になるのではなく、むしろ人体を含むすべての自然が不確実なリスクを内包するように、自然そのものが作り変えられてしまったと指摘する。そうである以上、やはり作り変えられた自然を直視しない、させない無知の構造を超える合理性を考察する事が倫理学の一つの役割になるのではないだろうか。そしてその先には、作り変えられてしまった自然(ベックのいう「第二の自然」)を所与のものとして受け取るか、それとも例えば1991年に第1回全国有色人種環境指導者サミットで採択された「環境正義の原則」のとりわけ第一章にうたわれる「母なる大地の神聖さ」に象徴されるような形で、汚染されていない自然自体を規範根拠として改めて定立する方向へ向かうか、が問われるだろう。
会務報告(所収:『倫理学年報』第72集(2023年3月30日発行))
高橋久一郎
ワークショップとして十回目である。「中仕切り」の機会とすることも考えたが、「事故」は終わってはいない。「株主代表訴訟」の判決も出たが、「甲状腺ガン」について裁判が始まるなど、「事故」の事実と責任の解明と検証は、むしろこれからである。そこで、今回は、山本剛史会員に、しばしば論じられる「リスク論」の適用の倫理学的意味と問題点について、「甲状腺がん」問題の論点と重なる形での報告をお願いした。このワークショップは、福島や避難地などで生じている「事実」の共有と、その倫理問題の検討をニ本の柱としているが、概して言えば、後者の場合の参加者が少ない。今回も、前回よりは少なかったが、40名ほどの参加をえて、熱心な議論を交わすことができた。