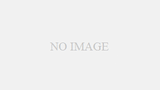〔アーカイブ・データ〕
・「第74回大会報告集」
・「会務報告」『倫理学年報』第73集(2024年3月31日発行)
・(当日資料)丹波博紀「日本倫理学会 連続ワークショップ「東日本大震災から見えてきたこと」アーカイブ・サイトについて」
第74回大会報告集
実施責任者 飯泉佑介
実施責任者 丹波博紀
石原明子
東日本大震災から見えて来たこと(11)
2013年に金井淑子会員、川本隆史会員、高橋久一郎会員の手によって始まった本連続ワークショップは、今回で11回目を数える。2011年3月に発生した東日本大震災と福島原発事故で被災し避難した方、そしてその支援や調査に取り組まれている方々をお招きし、お話を伺うこの企画には、「フクシマ」に想いを寄せる大勢の方が参加されてきた。ともすれば理論や思想をめぐる専門的な議論に終始しがちな学会で、何よりも当事者と当事者に近い方々の「声」に耳を傾け、対話し、内省を深める集いを10年間も継続してきたことは、とりわけ倫理学に携わる者たちにとって無二の意義をもってきたと思われる。塗炭の苦しみを味わってきた/いる方々のために、どこまで具体的な力になれたか/なっているかは各々自らを省みるしかないとしても、本ワークショップが、あれほど日本社会に衝撃を与えた「事故」に今一度向き合い、情報交換・意見交換を行い、場合によってはネットワークを築くような学術的・実践的な場として一定の役割を果たしてきたことは間違いない。忘却の圧力が強まる昨今、そのような場を確保すること自体が「倫理的」な重要性をもっているとさえ言えるかもしれない。
もちろん、昨年度の大会報告集の本ワークショップ概要で明示したように、「「中仕切り」できるほどにも「事故」は終わってはいない」。しかし、12年もの歳月を経て、徐々にフェーズが変化してきている可能性があることにも注意を向けてみたい。もともと東日本大震災の記憶が薄い若い世代が登場する一方、「事故」に対する受け止め方が複雑に交錯・変容し、従来の不正義が見えにくくなったり新たな対立や衝突が現れてきたりしているのではないだろうか。政府と経済界が原発再稼働にひた走る中、「事故」を真剣に受け止めてきた私たち自身の「位置」を再確認し、これまでの構えや考え方を改めて検討する必要があるのではないだろうか。
そこで、これまで労を取ってこられた金井会員、川本会員、高橋会員から、この度、飯泉佑介会員と丹波博紀会員がバトンを引き継ぎ、新たな体制のもとで本ワークショップを企画する運びとなった。3名の方には引き続きご参加して頂き、ともにワークショップを作っていきたいと考えている。
節目となる今回のワークショップでは、第1部と第2部からなる企画を予定している。第1部では、実施責任者の一人である丹波会員が、10年間のワークショップの記録をアーカイブ化する取り組みについて簡単に紹介する。第2部では、紛争解決学を専門とされる石原明子氏(熊本大学)に、紛争変容と修復的正義の観点から原発事故後の「コンフリクト」に関する報告を行って頂き、参加者との討議を行う。現在、水俣を拠点として水俣病発生後のコミュニティの紛争変容を研究されている石原氏は、震災直後の福島で被災者や避難者の聞き取り調査を精力的に行ってこられた。近年実施されている福島の若者と水俣の方々との交流活動の様子も踏まえて、さまざまな当事者の「いま」の「声」を伝えて頂けるだろう。なお、司会は飯泉会員が担当する。
【第1部 ワークショップ記録のデジタル・アーカイブ化について報告】
このパートでは、第1回目(2013年)以来の本ワークショップの実施概要をデジタル・アーカイブ化する取り組みについて紹介する。具体的には、専用のサイトを作成し、そこに各年の「大会報告集」掲載の概要、『倫理学年報』の会務報告を掲載することによって、誰もが確認し、吟味・検証できるかたちにする試みである。この作業により過去の実施記録は一覧で確認でき、通時的な観点から、個別に確認するのでは気づけないことにも気づくことができるようになる。
このデジタル・アーカイブは、
〈連続ワークショップ「東日本大震災から見えてきたこと」情報アーカイブ・サイト〉
https://311andethics.daynight.jp/
に設置されているが、ワークショップ当日にはこのアーカイブについても案内を行い、石原氏のお話との接続をはかりたい。むろんこのアーカイブは、今回限りのものではなく、随時更新していくことを計画している。
さて、こうした「ふり返り」の意図をもうすこし説明しておきたい。このワークショップは、倫理学や、これに携わる者たちが、震災・原発事故のいまだ終わらない「事実」と向き合う機会だったはずだ。それは端的に言えば、「事故」に対する自らの「位置」を省察するものであり続けてきたと言えるだろう。過去の実施記録をアーカイブ化し、その内容を「ふり返る」ことで、私たちはまずそうした、これまでの「位置」を知りたいと思う。
もちろん、これまでの「位置」を明らかにすることは、現在の、そしてこれからの「位置」を見いだすための作業である。たとえば、今回から、飯泉会員、丹波会員がワークショップの運営に加わり、実施責任者を引き継いだ。このことを多少反省すれば、そもそも「引き継ぐ」ということ自体が、震災・原発事故の「いま」に対する私たちの「位置どり」を示している。では、「私たちはどこにいるのか」――。こう自らに尋ねてみても、これに応えることは簡単なようで簡単ではない。そのための「よすが」が必要である。
また、こうした問いは、実施責任者だけのものでもない。このワークショップにかかわり、またこれからかかわるであろう、倫理学に携わる人たちの問いだとも言える。各自が応えるためにも、これまでの実施記録をデジタル・アーカイブのかたちで整理し、みなで吟味・検証できるようにすることは意味のあることだろう。
【第2部 石原明子氏による提題】
東日本大震災以降、東京電力福島第一原発事故(以下、原発事故と表記)の被災と再生の問題について、紛争変容・平和構築学の視点から関わり続けてきた。本報告では、その中で経験してきたことから話題提供をする。特に筆者が取り組んできた水俣と福島の交流についても、意義やこの12年での変化や新しい課題についても論じたい。
(1)紛争変容・平和構築学と原発事故―草の根倫理学としての修復的正義
紛争解決学は、私たちの心の中、関係性、社会におけるあらゆるコンフリクトに“建設的”に取り組み、解決をもたらすための実践的な学で、心理学・社会学・コミュニケーション学・経済学・文化人類学等の多様な学問を基礎にして学際的実践知を探求する学問として、北米等では高等教育における一分野として確立してきた。その中で、レデラック(J.P. Lederach)の紛争変容(conflict transformation)の考え方によれば、コンフリクトは、そこに人々の満たされないニーズや暴力(構造的暴力を含む)や不正義が存在することを示すサインであり、紛争変容では、目の前のコンフリクトを表面的に解消するよりも、そのコンフリクトの背景にある不正義や暴力的状況に気づいてそこに変化をもたらす(平和構築)とされている。原発事故後には、人間関係の対立・葛藤・分断・あつれきと称された状況(コンフリクト)が多く発生したが、これらは、被災者の苦しみ(満たされないニーズ)の発現であったのと同時に、原発や核をとりまく構造的暴力・不正義が可視化された状況でもあった。
筆者は、原発事故後に被災者間で起こった対立・分断・葛藤・あつれき(コンフリクト)からの変容に、紛争変容と戦略的平和構築、特に修復的正義の視点から取り組んできた。修復的正義は、紛争変容のアプローチの中でも、特に傷つけあった関係からの和解(関係修復)と正義構築を目指すアプローチであるが、実のところ、痛みを起点とした“草の根の倫理研究・倫理教育”であるように思えている。その意味は、痛みをめぐって関係した人たちが「どうするべきだったのか、どうしていくべきか」という倫理知を血肉を通じて探求し、その過程でその倫理が生き方として血肉となり、いのちを得ていくプロセスである。
(2)原発事故後に起こった対立・葛藤・分断、そのメカニズム、変容への道筋
原発事故後(直後から数年後)には、多くの人間関係の対立・葛藤・分断が起こった。避難をした人・しなかった人、賠償金をもらった人・もらわなかった人、放射能の危険性を心配する人・しない人など、事例が多くの研究や報道や芸術作品で、報告・表現されてきた。筆者の住む熊本県にも、多くの避難者(主に自主避難者)が避難・移住をして、その避難者コミュニティでも多くの分断や葛藤が起こった。沖縄や北海道を除けば、最もセシウムの降下量が少ないとされた熊本県には、比較的、放射能の健康リスクを強く心配する避難者の移住が多く、避難者の8割以上は関東以西からの避難者であった。そのコミュニティでは、放射能防御行動が不十分とみなされる人が「子殺し」などと言われて傷ついたり(この現象は、放射能防御行動をする人が「福島を危ないとみなす地域の敵」として阻害される福島内での現象と正反対:集団的心理的防衛機制による分断メカニズムの一つ)、関東圏からの避難者と東北からの避難者の深刻なあつれきなどもあったりした。
これらの分断や対立のメカニズムについて、筆者は主に「傷ついた社会(traumatized community)の現象」、「非対称紛争(ステークホルダー間に力の差があり、問題や矛盾が弱者に蓄積される)」の二側面に注目して、その変容理論として、修復的正義と非対称紛争変容(A.Curle)を意識しながら、変容実践の支援活動をしてきた。
(3)水俣と福島が出会う
上記の視点を活用した実践プログラムとして、筆者は福島の若手から中堅リーダーたちを水俣に招聘して交流するプログラムを、2013年から実践してきた。福島が抱えた構造的暴力は、まさに構造的暴力であるがゆえに、被害の認知も難しく、被害を認知してもその被害をもたらす構造の認知が難しい。主な目的は、①水俣と福島の問題構造が共通する中で、福島のリーダーたちに水俣病公害をめぐる水俣の歴史や現状を知ってもらい、福島が置かれた問題構造を福島の方々が自ら考えていくリソースにしてもらうこと、②共通する複雑な被害状況におかれた人たち同士が感情的に共に支えあえる関係性創出すること(共に泣く)、③構造的暴力からの変容の道筋は多様で、それでも未来はあるという希望を福島のリーダーたちに知ってもらうこと、であった。その中では、水俣の若手(公害の第二・三世代)と福島の若手(原発事故の第一世代)の間で過去と未来をめぐる対話なども生まれた。
(4)紛争は変容したのか。「水俣と福島」はどこに行く?
震災・原発事故から丸12年以上がたち、事故直後ほどには、人間関係の葛藤・対立の苦しみの訴えは原発事故の被災者たちからも聞かれなくなった。紛争は解消したのか、その根本原因構造が変容して紛争がなくなったのか。筆者は、根本原因構造が十分に変容したとは思えず、むしろ、その構造を保ったまま(あるいは再強化されて)紛争が「潜在化」されてきていることを感じている。福島イノベーションコースト構想に典型的に現れるように、国家プロジェクトとして福島にお金がつぎ込まれて、福島とくに浜通りは、広義の原発マネーなしには生活が成り立たない構造に再び追い込まれている。その中で国は、被害地域を双葉郡を中心とする浜通りに限定する戦略を明確に打ち出し、中通りなどの他の地域は非被災地として被害地域を支援するアイデンティティをもたせる教育にも力をいれる。「風評払拭」のための若手語り部育成にも力を入れている。その中で「水俣を学びたい」という層も変化してきた。以前は実害としての原発事故に悩む人たちの水俣訪問が多かったが、今は風評被害を問題視する人たちの訪問も増えた。一方で「風評被害で苦しいのです」と福島から言われれば「水俣もそうなんです」と“安易に”共感してしまう水俣側の癒えぬ傷も、まだここにあるのである。「水俣と福島」の旅路も新しいフェーズにはいったのかもしれない。
関連資料
◆(当日資料)丹波博紀「日本倫理学会 連続ワークショップ「東日本大震災から見えてきたこと」
アーカイブ・サイトについて」
会務報告(所収:『倫理学年報』第73集(2024年3月31日発行))
丹波博紀・飯泉佑介
十一回目の今回は、紛争変容・平和構築(とくに修復的正義)を専攻される石原明子さん(熊本大学)に、提題報告をお願いした。石原さんはアメリカから帰国された二〇一二年以降、上記の専門を活かし、被災された方たちと関わっておられる。ワークショップ当日はまずそうした経験をふり返っていただき、次いでフロアを交えて修復的正義の可能性とその容易なさをめぐって話し合った。また、今回は実施責任者の引き継ぎも意図されており、その前提となる過去十回の記録をアーカイブ・サイトで公開していた(https://311andethics.daynight.jp/)。そこで論議は、この連続ワークショップが注視してきた「女・こどもの倫理」「リスクの論理」と石原さんの発題とのかかわりへと深まった。なお、参加者は四二名に及んだ。