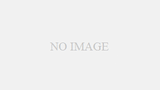〔アーカイブ・データ〕
・「第66回大会報告集」
・「会務報告」『倫理学年報』第65集(2016年3月30日発行)
・(関連論文)丸山徳次「『母子避難』の悲劇性と持続可能社会への希求」『龍谷哲学論集』第29号(2015年1月31日発行)
・(関連論文)丸山徳次「『母子避難』の根源的な問題 : 生産と再生産の矛盾」『龍谷大學論集』第489号(2017年3月7日)
第66回大会報告集
東日本大震災から見えてきたこと(3)
――女・こどもの倫理(3)
実施責任者 高橋 久一郎(千葉大学)
長い目で見れば「忘れる」ことは大事なことであると思う。しかし、「しばらく」は忘れてはならないことがある。二〇一一年の大震災との関わりで、そこに露わになった倫理学の問題について「生命の倫理」の可能性と重要性という全体テーマのもとにワークショップを何回か開催したいと思っている。
ということで、昨年に引き続き、三度「女・こどもの倫理」というテーマで開催する。理由は単純である。昨年と同じことを繰り返すが、時が過ぎ、再び、社会的にも、そして、倫理学会的にも、提示された問題が忘れられようとしているからである。
他方で、「リスク(と管理)の論理」が強力に展開しつつある。この論理は、計算する理性の延長上にあり、いわば「魂の向け変え」を求める「女・こどもの倫理」よりもはるかに理解しやすい。私自身は、この論理に「真っ向から反対」というわけではない。つまり、「女・こどもの倫理」と不可避的に対立するものでもないとも思っている。それどころか、相応しく論ずるならば、「女・こどもの倫理」を「補完」し、さらには「相補」しあうものともなりうるとも思っている。だから、そろそろ「リスクの論理」についても開催したいと考えている。リスクの論理の具体的な手法やその問題点だけでなく、この論理を語るさいに最も重要な具体的な数値についてもかなりのところまで見ることができるようになってきたからでもある。しかしそれだけにもう一度、今年は出発点に立ち返って、「女・こどもの倫理」というテーマでワークショップを開催しようと思う。最初にワークショップ開催に手を挙げた時の趣旨の一部を再録しておきたい。
「子供を連れて「逃げた」母親がいる。「留まった」母親もいる。どちらにも賞賛と非難がなされた。何が問題とされたのか?何故それが問題とされたのか?何となく分かったように思っているかもしれないが、ここにある問題も、また問題を論ずる論理も、必ずしも明らかではない、あるいは、少なくとも共通の理解とはなっていないように思われる。」
今回は、「「逃げた」母親」であり歌人である大口玲子さんと丸山徳次会員に提題を頂くことにした。
大ロさんには、具体的な事実と経験について表現者としての立場から改めて照射していただき、丸山会員には、具体的な事例を理論的な検討に繋ぐ場面での視座について話していただけると思っている。
母子避難(自主避難)を「語る」ことの難しさ
大口 玲子(歌人)
0 避難後の自分を語ること
・晩春の自主非難、疎開、移動、移住、言ひ換へながら真旅になりぬ
筆者は東日本大震災発生時、宮城県仙台市に夫と息子(当時二歳)と暮らしていたが、放射能汚染が子どもの健康に与える影響を心配して震災後八日目に仙台を離れ、現在は宮崎県に住んでいる。震災後の自分を語るとき、「危険だと判断したから仙台を離れた」というだけのことを言葉にすることの難しさを感じ続けているに宮城県内はもちろん、福島県内でさえそこで生活している人がたくさんいる現状からすれば、他人に自分を語るとき時に自分が圧倒的な「マイノリティー」であり「変わりもの」であることを意識せざるを得ない。
1 地域(避難元)に対して
・八日ぶりに髪も洗ひて湯につかり後ろめたさが深刻になる
「今も問題や困難を抱えている地元に残って復興に協力すべき」「もう大丈夫だから帰るべき」「仙台での生活を危険と判断するのは風評被害につながる」「本当は避難したいけれどさまざまな事情があって避難できない」というような意見や考え方を前に、後ろめたさを感じることがある。
2 夫、親族に対して
・欠かさずに夫は観るといふ「あまちやん」に原発事故はいかに描かれむ
放射能汚染について、自分の両親や夫の両親との間には大きな意識の違いがある。震災後も東北で生活を続ける夫は、避難について理解をしてくれたが、その後離れて暮らすなかで意識のずれが生じている。
3 避難先の地域の人々に対して
・被災者といふ他者われに千円札いきなり握らする老女をり
被災者として「何が必要ですか」と聞かれたり、お金や食料、物資等をいただいたりすることが多かった。また、「いつ帰るの?」と聞かれることもあった。「被災者=支援」というだけではなく、同じ地域で共に生きる者として、地域の問題を共有し一緒に考えていくことができる場を作っていきたい。
4 同じ立場である避難者に対して
・家が無事なのに仙台を離れたといふやましさをぽちりともらす
宮崎の避難者の会では、当初は、同じ立場・同じ境遇という「共感」をもって避難者の会に集まっている部分が多かった。そのうち、父親も宮崎に移住した家族、地元と宮崎を行ったり来たりする家族、しばらく宮崎に滞在したがやはり地元へ帰った家族など、それぞれの「差異」が出てきて、その差異をお互いに受け入れ、認め合う方向へ向かった。
5 取材者(マスコミ)に対して
・「福島の人は居ませんか(福島でなければニュースにならない)」と言はる
母子避難をしている母子の「健気さ」「大変さ」のみを取り上げられ、「なぜ避難しているのか」という根本的な問題は話題にならない。一面的なイメージが作られていると感じている。
6 歌人(表現者として)
・なぜ避難したかと問はれ「子が大事」と答へてまた誰かを傷つけて
作品への批判であっても、生き方への批判と受けとめてしまう。また、放射能汚染や母子避難の問題について、意識の異なる他の作者の作品を、短歌作品として冷静に受けとめることができない。素材が生々しすぎて、文学の話題としてとらえることができない。
以上のような点について、自分の生活と短歌作品から考えたい。
引用:大口玲子歌集『トリサンナイタ』二〇一三(角川書店)
「母子避難」の根源的な問題
丸山徳次(龍谷大学)
世界で最初の環境汚染にもとづく有機水銀中毒事件である水俣病事件は、二度にわたる「政治決着」と最高裁判決にもかかわらず、六〇年を経過しようとして、未だに「解決」されないばかりか、なお新たな「被害者」が登場し、新たに提訴がなされさえしている。初期の急性劇症型の印象に呪縛されたことは科学者たちの自己批判をも生みだしたが、むしろ加害責任を負うべき当の行政が、被害の全貌を調査することなく、それ故に水俣病の「病像」を曖昧化させたまま、「救済」(?)対象を縮小的に「線引き」する主体となったことが、長期微量汚染による慢性型ないし遅発性の水俣病による「未認定患者」の問題を、今に至るまで引き起こしているのである。高齢化によって様々な苦しみを増している胎児性やニ世代目の水俣病患者たちの現況を、水俣病事件のこれまでの経緯と併せて見るとき、フクシマ(片仮名表記する理由は別途述べる)における「低線量被曝」の被害のゆくすえに、どうしても不安の眼が向く。地域独占の国策私企業が地域生態系を破壊し、公益と公衆に被害をもたらした点で、構造的に、フクシマはミナマタと同じ「公害」事件の様相を呈しているのである。
「環境正義」論の立場から水俣病事件を批判的に回顧することを一つの仕事としてきた私の主張によれば、公害の経験によって学んだことは、世代内および世代間の不正(不正義)を前提にした経済成長と「豊かさ」の追求は容認できない、ということであり、それゆえ経済成長至上主義から脱却し、世代内および世代間の正義を体現した「公正な持続可能社会」を追求することが、公害の経験から出てくる規範的要求なのだ、ということである。
ミナマタとフクシマに共通する最も基本的な点は、「中央と地方」の差別化を背景としながら、経済成長を至上価値とする経済社会において、政治権力と経済権力の複合体が一部の「犠牲」を黙認し、地域生態系と家族と共同体を危機に陥れ、それらに支えられた「生活」を破壊し、「棄民」をもたらしたことである。
二〇一二年一一月の関西倫理学会シンポジウム「専門家と信頼」の提題者だった私は、「信頼」概念の批判的な吟味を行なうとともに、日本において最も有力と見なされている社会心理学による信頼研究が、電力企業にたいする公衆の信頼度を高め、原子力発電の開発を推し進めることに向けられていた事実を分析し、「信頼への問いの方向性」そのものを間うことが「信頼の倫理学」の課題であると論じたが(『倫理学研究』第四三号、二〇一三年)、なおフクシマの問題に直接関与することを避けていた。ただ、ここでの拙論は、自主避難者を調査研究していた別の社会心理学者の支持を得、私自身が「母子避難」への関心をよりいっそう深める契機ともなった。
昨年度の本ワークショップで「母子避難」の問題に強く惹かれた私は、金井淑子氏によって教えられた短歌の世界に、自分でもいくらか立ち入り、短歌作家たちの間で一種の論争が起こっていることに「母子避難」のよりいっそうの悲劇性を感じ、「「母子避難」の悲劇性と持続可能社会への希求」(※)と題した発表を二〇一四年一二月、日本現象学・社会科学会で行ない、ようやくフクシマの問題に応答する方向を見出したように思う。
(※)アーカイブ管理者より:
本発表の論文は「龍谷大学図書館蔵書検索システム」より閲覧可。
下掲「関連論文」の項目も併せて確認。
「許可車両のみの高速道路からわれが捨ててゆく東北を見つ」「なぜ避難したかと問はれ「子が大事」と答へてまた誰かを傷つけて」といった大口玲子氏の歌には、孤独な屈折した自己が読み取れる。しかしそれを、「良心的な逡巡」のポーズにしか過ぎないという阿木津英氏の批判もある。他方では、岩井謙一氏の「放射能エゴイズムを喚起して怖い東北捨てられてゆく」「わが子さえよければよきか狂いたる母性本能深く冷たし」「母子避難ありて夫は置き去りに理性にあらぬセンチメンタル」といった歌もある。
「母子避難」という言葉そのものが、すでにこの社会の価値観を表現している。もし私たちが「命のつなぎ」(reproduction)の仕事を、財やサービスを生む生産労働よりも価値の高いものと思うならば、そしてその「命のつなぎ」の仕事を、女性だけではなく男性も平等に担うべき大切な仕事として社会全体が認め、その価値づけに基づいて社会が編成されるならば、「母子避難」などといった事態と言葉は生み出されはしないだろう。「なぜ人間の生命を産み育て、その死をみとるという労働(再生産労働)が、その他のすべての労働の下位におかれるのか、という根源的な問題」(上野千鶴子)が、「母子避難」によって間われているのである。
昨年度のワークショップへの案内の文言を(さらに一年繰り下げて)繰り返しておこう。三年前の大会の共通課題の実行委員、提題者、そして関連して開催されたワークショップ・主題別討議の提題者、さらには、一昨年・昨年のこのワークショップの出席者、そしてもちろん、はじめて「あなた」にこのワークショップに参加して頂ければ幸いである。
関連資料
◆(関連論文)丸山徳次「「母子避難」の悲劇性と持続可能社会への希求」『龍谷哲学論集』第29号(2015年1月31日発行)★『大会報告集』中で言及あり。文中にて本ワークショップについて言及★
※リンク先:龍谷大学機関リポジトリ
◆(関連論文)丸山徳次「「母子避難」の根源的な問題 : 生産と再生産の矛盾」『龍谷大學論集』第489号(2017年3月7日発行)★第66回ワークショップでの発表を拡大・修正した論考(文末に言及あり)★
※リンク先:龍谷大学機関リポジトリ
会務報告(所収:『倫理学年報』第65集(2016年3月30日発行))
高橋久一郎
連続ワークショップの三回目として今回は、多く見られ今も継続している「母子避難」に関して、経験者としての表現を公表してきた歌人の大口玲子氏には、母子避難(自主避難)を「「語る」ことの難しさ」として当時の動きと現在の時点での回顧と問題について、継続的にワークショップに関わってきた丸山徳次氏には「「母子避難」の根源的な問題」と題して(今も解決したとは言えない)「水俣病問題」との異同などにも触れながら倫理学的な論点についての提題をお願いし、その後、会場参加者と細部にわたる質疑、そして熱心な討論を行なった。大口氏の提題は、まもなく別に発表されるはずである。