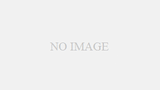3月11日に発生した東日本大震災とそれに伴う原発公害は、この科学技術文明社会の大きな推進力の一つである学問のあり方に深い疑問を投げかけるものでした。
たとえば、この間、「想定外」という言葉が頻繁に使われました。では学問にとって「想定外」の未来とは何なのでしょうか、また「想定内」の未来とは。このことと社会や国家、企業はいかに関係し続けてきたのでしょうか。
このシンポジウムでは、参加者みなで3月11日に照射される学問・教育・大学の姿を問い、「学問の未来」について議論し合いたいと思います。
〇 登壇者 (敬称略/五十音順):
飯泉佑介 (修士課程・哲学)
川本隆史 (教員・倫理学)
鬼頭秀一 (教員・環境倫理学/科学技術社会論)
最首悟 (元助手・問学)
丹波博紀 (博士課程・思想史)
長谷川宏 (哲学者)
星埜守之 (教員・フランス文学)
*学生・教員は東京大学所属。
〇 日時:
2011年9月17日(土)
12時半開場、13時~17時
〇 プログラム:
13:00~15:05 第一部 学問をしている身として
【発言順】
丹波 博紀
飯泉 佑介
(小括:川本 隆史)
星埜 守之
川本 隆史
鬼頭 秀一
(同:最首 悟)
長谷川 宏
最首 悟
(同:丹波 博紀)
15:05~15:20 休憩
15:20~17:00 第二部 総合討論:学問にとって未来とは何か
*進行具合により時間は変更される可能性があります。
〇 場所:
東京大学駒場キャンパス
5号館511教室
・アクセスマップ:http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/map02_02_j.html
・キャンパスマップ:http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam02_01_04_j.html
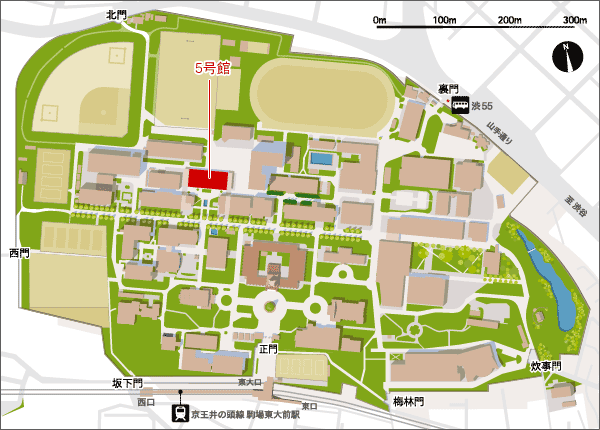
〇 参加費:無料(ただし会場でカンパをお願いする場合があります)。
〇 当日配布パンフ:ダウンロード
〇 チラシ:ダウンロード
〇 主催:シンポジウム「学問にとって未来とは何か」実行委員会
〇 お問い合わせ先:saishjuku@yahoo.co.jp(丹波宛)
* 参加に際して事前の予約などは必要ありません。直接会場までお越しください。
〇 総合討論提題文: 学問にとって未来とは何か
最首 悟
学問は、正義と森羅万象に対する愛によって、平和にして豊饒な人類社会の実現を目指す知的な営みであり、そのような営みをなすコスモポリタンのコミュニティーである。学問の示す未来は希望と変化可能に充ちている。端的に学問は人類の幸福を目指す理性的な営為である。子どもや若者に学問への誘いを語ろうとすれば、このようなメッセージになるはずだ。
現にマイケル・ポラニーは、純粋な学問の精神は、正義と理性に対する信念に基づいており、世界が学問(科学)を必要とするのは「何よりも善き生活の範例」だからだと言った。科学のコミュニティーは、一定の信念への忠誠と権威、異論の調停、個々人の自由および自発性と協同の目的との調和を保証しているのであり、たとえドイツの科学者であろうが、日本の科学者であろうが、その態度を共有している。科学社会は、理想的な、あるいは自由な社会組織の範例なのだ。
すでに半世紀以上前、まさにそのような科学を夢見た身には、大学の片隅でひそかに暮らせたらという謙譲な思いと、貧困と不正のない社会の構築への寄与という熱い思いは同居していた。ポラニーは、第二次世界大戦後の情況において、破壊的懐疑主義が新たな情熱的な社会的良心と結びついた、すなわち「人間精神に対する完全な不信が過剰な道徳的要求と結びついた」状態に対して、科学の理想の擁護に固執しなければならないとした。
ポラニーの攻撃は共産主義に向けられたが、1968年、この破壊的懐疑と情熱的な社会的良心は、学生という層によって、共産主義も大学をも攻撃し、解体しようとした。特に日本においては、ファッショも軍部もやらなかった暴挙という印象さえ生まれたが、大学、学問、科学、技術、研究、研究費、講座制、国家、祖国、資本、精神労働、企業が様々な組み合わせ、からみあいとして問われた。なかんずく学生不在の大学とポラニー的科学共同体の不在が問われたのである。
しかし、ハンナ・アレントは、17世紀に始まった科学組織を指して、「全ての歴史の中で最も潜在能力のある権力発生集団の一つとなっている」とした。自然征服のために自分たちの道徳的標準と道徳的通念を発展させてきた組織は、自らの活動のため、時計に代表される技術を開発し、しかもその結果には無関心で責任をとらない。科学共同体は人間関係の網の目の中へとは活動しないのだ。
学問・研究が客観的対象の仕組みを追究するかぎり、人間は主役とならざるを得ず、人間が人間に対して責任をとらざるをえなくなる。世界は無根拠化し、その中で人間は立ち枯れてゆく。自分で自分の首を絞めてゆく学問・研究に未来はない。
私はいま「問学を」と呼び掛けている。理性的な追究の結果として浮かび上がってきた「いのち」の認識不能性に対して、その不能性の根拠を問うこと、ならびに、その不能性を自明として、「いのち」をなおざりにして生きる、あるいは生きられるとは何かを問い続けることを問学としたいのである。
しかし17世紀からの(自然)科学は、「なぜ」という問いを「いかに」という問いにずらし、世界の物理的化学的仕組み(からくり)の解明に的をしぼった。その結果は無根拠の世界の必然的運行をベースとした、観測者依存の事象と予測不能の複雑系の招来であった。その探究の過程において、精密機器開発の技術が要求され、宗教改革、労働観の変遷と相まって、技術文明と、絶えざる競争を強いられる市場原理に基づく資本主義のなかに、科学が位置づけられることになった。
無意味化した世界の中で、競争、進歩のみに意味を求め、しかも納期という未来に縛られた技術成果主義は、人間に焦燥と強度のストレスをもたらし、生きもの全般に破壊的影響を及ぼす。「なぜ」と問う学問が消失したとすれば「問学」として復活させねばならい。
新たな枠組みが求められている。それは「いのちは世界」として提示される。世界内存在としての人間は分有の「いのち」である。いのちに包摂された「いのち」である。森羅万象はいのちに包握された「いのち」である。いのちは分けられずわからない。言語(記号)をもってその意味を物語ることがいのち(世界)についての「なぜ」を新鮮にし、いのちの豊饒さを体感させる。森羅万象の「いのち」の仕組みを追究する科学は、「なぜ」を深める有力な営為として位置づけられることによって、意義を回復するといわねばならない。
*1「純粋科学の社会的メッセージ」1945、『自由の論理』長尾史郎訳、ハーベスト社、1988
*2『人間の条件』1958志水速雄訳、ちくま学芸文庫、1994
〇 シンポジウムに向け~問うことから始めよう~
丹波博紀
学問にとって未来とは何か。
東日本大震災にともなう福島第一原子力発電所での原発公害が3月11日に発生した。その日以来、頻繁に耳目に触れるいくつかの言葉があるが、そのなかでも特に “想定外”という言葉は学問の特質を端的に示しており、より考えたい言葉である。この言葉は政府と東京電力、またはこれらに深くかかわる学者・科学者を中心にして発せられたものだった。
この言葉が含意する学問の特質とはつまり、学問とはそもそも世界を要素・部品に分け、それを分析し、その結果見込まれる“想定”のもと、いわば未来を立てる(予測する)営みであるということだ。すると“想定外”の言い換えは、“分析が至らず、予測が外れた”になるだろうか。
この“至らなさ”についてさらに触れれば、実際この間、上記の者たちにかぎらず、学問・科学にかかわる多くの者が問題としてきたのは、この“至らなさ”だったように思う。すなわち、原発公害を引き出した学問のあり方は“至らない”ものである、だからそれを問い、真に必要なもののための有用な学問を示そう。学問はいずれにせよ何ごとかに対して、誰かに対してか有用であるべきであり、このこと自体は不可疑の前提なのだ。
もちろん、“至らなさ”を問題にするとき、当人たちが真剣そのものであることは疑う余地もない。だが、そもそも以上述べてきたような学問の根本的な特質自体が原発公害の根源にあるのではないかという疑いや、そうした学問にかかわる、関心をもつ自分とは何なのかという自問、そして本来“学生(がくしょう)の共同体”であるべき大学が、昨今、特に国家・資本の有用にのみかなうよう整備され、いわば企業化している情況への異議申し立ては、そこから必ずしも明瞭には聞こえてこない。
言うまでもなく、歴史上このことに対する批判が全くなかったわけではない。例えば1960年代末の世界的な学生叛乱では“大学とは何か”が問われたが、その問いは40年間くすぶりつづけてきた。だが、いずれにせよ、今を生きる私たちはそれを十分にとらえも、受け取ることもしないまま、この3月11日を迎えたのだった。この日、私たちの前に現れたのは、“なぜ学ぶのか”“大学とは何か”という問いを決して無視できない情況だった。この情況が、私たち自身をうずかせ、やましくさせる、それらが振り切れるどころか日増しに強まり、溢れかえるような思いにさせる。
だから、私たちは、教養学部のある駒場キャンパスにおいて、自分の手と足で模索して“自己対象化”と“自己形成”をはかる、この“教養”の場で、3月11日に照らし出される私たち自身を深く見つめ、学問という営みそのものを疑い、問うことから始めたいのだ。
学び問うことにかかわり、関心をもつあらゆる人に、このシンポジウム「学問にとって未来とは何か」への参加を呼びかけたい。