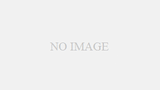掲載:『毎日新聞』2020年3月9日朝刊
川野里子
東日本大震災の起こった春以来、福島の姑は庭仕事を諦めざるを得なくなった。原発事故によって見えないものが見慣れた庭を覆い、何かがすっかり変わった。手入れされていた庭に草が目立つようになり、庭木が繁り放題になっていった。
ふくのしま花も実もある平凡なふるさとともう誰も笑えず 駒田晶子
この庭の一隅にシダ科の植物であるイワヒバが這うように繁っている。私が結婚した時、父が根を濡れた新聞紙にくるんでこの家に届けたのだった。この目立たない植物を珍しがった姑は、大切に育ててくれた。冬は藁を被せ、夏は日傘をさしかけて。勝手口の最も家族の行き交う一隅で、イワヒバは私の代わりに処を得て繁っていった。
五年ほど経って除染が決まり、地表から二センチ、庭の土が剥がされることになった。すっかり姿を変えてゆく庭。その隅に残ったイワヒバも丸ごと剥ぐほかない。だが、姑は頑として「なんね(ダメだ)」と承知しなかった。雨樋の水が注ぐその場所は線量が高かったが、姑の気迫に圧されてイワヒバは残されることになった。今もそこにこんもりと繁っている。
若かった私が気づかぬまま過ごしてきたものがそこにある。「何とか根付きますように」という姑と私の父の間に流れた祈りだ。それはいかにも古風な「家」に「嫁」が入るという観念であり、先祖代々子々孫々という過去から未来へと流れる時間への信頼であった。父も姑もこの不束な娘をその川に植え付け、永く永く生きよ、と祈ったのだった。それは現代という時代の傍らにひっそりと流れ続けていた時間の伏流だ。
原発事故以後見えにくくなった未来を前に、ふっつりと途絶えたかに思える川は今どこへどのように流れようとしているのだろう。あのイワヒバにも春はやってきて、ひっそりと新緑が迫り出そうとするのだけれど。
ああ春の向こうからどっと駆けてきてふくしまの子らがわれの手を引く 齋藤芳生
(かわの・さとこ=歌人)